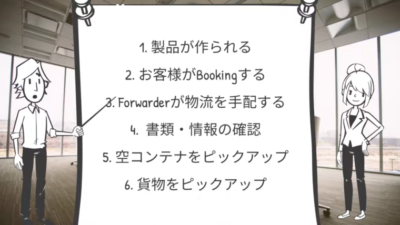2020.04.23
物流における実重量と容積重量の違いとは?LCL・航空輸送・トラック輸送でそれぞれ違う容積重量の計算方法を紹介します。
主に航空便で貨物輸送をする時に気をつけないといけないのが容積重量です。しかし、容積重量は航空便だけでなく海上輸送のLCLやトラック輸送、そして倉庫でも使われる重さとなります。 実重量と容積重量の違いをよく理解をしていなければ正しい物流コストを算出することは出来ません。今回は物流における容積重量と実重量の違いと、各種物流においての容積重量の計算式についてご説明をしていきたいと思います。 実重量と容積重量 まず実重量と容積重量とは何でしょうか?これは物流業界では基本の重さに対する専門用語です。実重量とは実際の重さのことで、そして容積重量とは貨物の大きさを重さに変換した時の重量のことです。 そうなんです。容積重量が物流業務での重さを理解する肝なんです。 アニメーション動画で容積重量について解説 Chargeable Weigthとは? より分かりやすく理解できる為に、貿易の実務で一般的に使用されるChargeable Weightを一緒にして説明をしていきます。 Chargeable Weightとは貨物の大きさと重さを比較して大きい方を費用換算に使う重量のことです。大きいものと重いものという単位が違うものを比較するというのがポイントです。 物流業では限られたスペースでビジネスをしている 物流では限られたスペースを使ってお客様の貨物の配送や保管をします。 これは船会社、航空会社、トラック会社、倉庫会社のような限られたスペースを使ってビジネスをする場合、大きさや重さのどちらか一方の単位だけで費用換算をするとフェアではない場合が出てくるからです。 同じ1トンを扱うにもこれはフェアでしょうか? 例をあげましょう。航空輸送で「1トンの水」と「1トンの綿」を運ぶ場合どちらの方がスペースを多く取るでしょうか? 水は重いけれど かさばりません。しかし綿は軽くて非常にかさばるので、水より遥かに大きなスペースを使います。 航空会社からしたら同じ1トンという実重量で費用換算してしまうと、かさばる綿の場合はスペースを大きく使うので損をしてしまいます。 まず単位を同じにして比較をする 貨物の大きさと重さが全く違うとフェアではなくなってしまう。。そうならない為に貨物の容積を重量換算する容積重量が使われます。 そして実重量と容積重量を比較して どちらか大きい方をChargeable Weightとして費用換算するのです。 それでは実際に実重量と容積重量の比較をみていきましょう。 海上輸送LCLと倉庫での容積重量の計算方法 まず海上輸送のLCLと倉庫の場合ですが、大きさと重さを比較するルールがあります。 このルールは絶対に覚えておかなければいけません。 例えば ・貨物の実重量:1.5ton ・貨物サイズ:0.8m(縦) × 0.9m(横) × 1.7m(高さ) = 貨物の体積: 1.22m3 先ほどの 「1m3=1トン」というルールを使えば1.22m3=1.22トン(容積重量)となります。 そして実重量が1.5トンで容積重量は1.22トン。この場合の大きい重量(Chargeable Weight)は実重量の1.5トンとなります。 航空輸送での容積重量の計算方法 次に航空輸送での容積重量の換算法を見てみましょう。 航空輸送では先ほどの海上輸送や倉庫でのルールとは違うものになります。 先ほど説明した例とは違い航空便では一般的にcm2とkgが使われます。また会社によっては6,000ではなく5,000でわる場合もありますが、6,000の方が一般的です。 例をあげましょう。 ・貨物の実重量:50kg ・貨物サイズ: 70cm(縦) × 90cm(横) × 90cm(高さ) = 貨物の体積: 567,000cm3 568,000(体積cm3) ÷ 6,000 = 94.5kg(容積重量) 実重量が50kg, 容積重量が94.5kgということでChargeable Weightは容積重量の94.5kgとなります。 混載トラックでの容積重量の計算方法 そして日本での混載トラックの場合、基準となるルールですが これも同様に単位には気をつけてください。 例を見てみましょう。 ・貨物の実重量:50kg ・貨物サイズ:0.7m(縦) x 0.9m(横) x 0.9m(高さ) = 体積:0.56m3 0.56(体積m3) × 280 = 156.8kg(容積重量) 実重量が50kgで容積重量は156.8kgです。この時のChargeable Weightは 容積重量の156.8kgとなります。 航空便でのChargeable Weightを計算しよう 最後にケーススタディーをしてみましょう。 2リットルの水が12本入った箱があります。これを100箱、航空輸送で出荷をする予定です。 箱のサイズは縦90cm、横30cm、高さが40cmです。 この貨物を輸送する時のChargeable Weightはいくつになるでしょうか? まとめ いかがだったでしょうか。今回は容積重量と実重量の違いと計算方法について解説をしました。 これは物流業界では基本の専門用語で計算方法はルールとして覚えなければいけません。LCL、航空輸送、倉庫、トラック輸送の実務で頻繁に使われる内容ですので今回の動画の内容を理解をして、使えるようになりましょう。