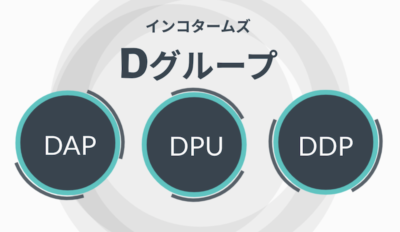2020.05.27
InvoiceとPacking Listの書き方について解説!貿易書類のサンプル・テンプレートとしてダウンロードも可能です。
今回のテーマは貿易におけるINVOICEとPACKING LISTの書き方について分かりやすく解説していきたいと思います。 まず、そもそもINVOICEとPACKING LISTとは何でしょうか? 貨物を輸出するときには必ず作らなければならない書類、輸入するときには乙仲や通関業者へ提出しなければならない書類、との認識を持っていらっしゃる方は多いと思います。 では実際にどのような役割があるかについて確認していきましょう。 InvoiceとPacking Listの書き方を動画で解説しました 貿易におけるInvoiceの役割 まず最初にINVOICEの役割についてです。 INVOICEは日本語にすると「請求書」です。皆さんが通信販売などで商品を購入したときに商品とともに送られてくる請求書、それのことです。 貿易では、INVOICEを元にどんなものが輸出入されているかの確認や、輸入国でいくら税金を払わなければならないかの計算がされます。 なので「仕入書」や「送り状」と訳したほうがしっくりくるかもしれません。関税法上、輸出入の申告においてほぼ例外なく必要となる書類です。 貿易におけるPacking Listの役割 続いてPACKING LISTの役割です。こちらは日本語にすると「梱包明細書」です。 貿易ではPACKING LISTでどの貨物がどれくらいの数量で輸出入されているか、どのような荷姿で梱包されているか、貨物にどのようなマークが付けられているか、などの確認をします。 つまりInvoiceもPacking Listもどちらも貿易にとってなくてはならない書類ということです。 なので たかが仕入書、梱包明細書と思わず、正確な情報を明確に記載することが重要です。 絶対にやってはいけない事 間違っても、税金を安く済ませたいから商品の価格をわざと低く記載したり、運賃を節約するためにボリュームを小さめに記載したりすることはあってはならないことです。 もし仮に、乙仲業者や通関業者はうまくやり過ごせたとしても税関の事後調査で指摘されて多大な追加税を払うことにな理ます。 また船や飛行機に積載する段階になって判明して輸出できなくなり、貨物の引き取りや船のキャンセルで余計なお金や時間がかかったりするのは目に見えています。 そういったことを防ぐためにも、貿易にとって大切なこれらの書類の書き方をしっかり覚えておきましょう。 InvoiceとPacking Listの例 - ダウンロード可能 「書き方の前に書式はどこにあるの?」という方もいらっしゃるかもしれませんが、INVOICEもPACKING LISTも特定のフォームはありません。 もし1から作る必要があるという方がいらっしゃいましたら、弊社で使っているものをテンプレートとしてお使いください。 こちらからダウンロードすることが可能です。 【形式:エクセルファイル】 ・Invoice ・Packing List ・Shipping Mark Invoiceの書き方 それではまずINVOICEの書き方から解説します。 INVOICEには輸出入者情報に加えて、輸出入される物の品名・数量・金額、船やフライトの便名などの輸送情報などが主に記載されます。基本的には英語表記です。 そしてこのINVOICEが請求書としての役割にプラスして輸出入時の通関書類にもなるのです。つまりINVOICEを見ればその貿易の内容がわかるように作成することが重要です。 また、記入は細かく正しく分かりやすくというのが大切です。 Invoice作成時のポイント ここからは基本的な記載事項についてお話します。 売り手と買い手の情報 輸出者(=送り主、シッパーとも言います)の社名・住所・電話番号・FAX番号などを記載します。 同じように輸入者(=受取人、コンサイニーとも言います)の社名・住所・電話番号・FAX番号などを記載します。 Invoiceの番号について インボイス番号の決め方に特に決まりはありませんので、任意の番号で構いません。 連番にする、日付を利用する、送り先の国名や会社のイニシャルを入れる、などルール決めをしておくと便利でしょう。今まで見てきた感じではやはり日付を利用されているパターンが多かったです。 本船情報について 利用する飛行機や船の便名、出港日も記載します。業者に依頼していて不明な場合は確認しましょう。 支払条件はその貿易取引のものを正しく書いてください。電子送金決済を意味するT/Tなどが多いです。 到着する港や空港の名前、国名も記載しておきます。 取引条件について 貿易取引条件の明記も必要です。インコタームズで規定されている取引条件に沿って記載しておけば問題ないでしょう。 FOB OSAKAやCIF SHANGHAIといった表現で大丈夫です。 貨物の詳細情報について そして重要な、貨物の明細についてです。輸出入する貨物の品名、個数、単価、合計金額を記載します。 通関業者はこの品名を見て申告する税表番号を決めていきますので、分かりやすく詳しく書くことがポイントです。 できれば品名だけでなく材質や使用目的なども書いてあるとよいでしょう。材質ならWOODENやSTEEL、使用目的ならFOR CARなど書いてありますと通関業者はとても助かります。 シッピングマークについて シッピングマークはこちらも規定のものはありませんので任意で構いません。 オーソドックスなものは上から会社名、向け地、箱の番号(連番など)、生産国もしくは輸出国名(MADE IN JAPANなど)でしょうか。 サインして完了 最後に輸出者の名前と、担当者のサインを記入します。 近年はサイン入りのINVOICEでないと輸入申告ができない国も増えていますので、しかるべき担当者の方が忘れずにきっちりサインをするようにすると良いですね。 Packing Listの書き方 続いてPACKING LISTの書き方です。 PACKING LISTの内容は実はINVOICEとほぼ変わりません。フォームも同じものを使っている会社がほとんどです。 貨物の単価や合計金額ではなく、貨物の大きさや重さ、梱包前の重量と梱包後の重量などを記載します。 ケースの数や、どのケースに何が何個入っているかなども書かれていると、もし貨物が検査になったときにスムーズに進みます。 InvoiceとPacking Listをまとめる 実務上の話をしますと、実はPACKING LISTは、ほぼ例外なく必要なINVOICEとは違い、他の書類(B/Lや他の明細書)などで貨物の個数重量がわかるような書類があればなくてもOKです。 なので、輸送する貨物が少ない場合は、INVOICEとPACKING LISTを一つにまとめてしまっても問題ありません。 もちろん、貨物の管理には大変有効な書類ですし、到着地で貨物が行方不明になってしまった場合(嘘のような話ですが本当にあります)にもPACKING LISTがあると捜索に役立ちます。 ぜひ正確でわかりやすいPACKING LISTの作成も心掛けて頂ければと思います。 まとめ 以上がINVOICEとPACKING LISTの書き方となりますがいかがでしたでしょうか。 慣れてしまえばそれほど難しい書類ではありません。あらかじめフォーマットさえ決めてしまえば後は輸出入の都度、必要事項を書き換えるだけで作成することができるでしょう。 繰り返しになりますがINVOICEもPACKING LISTも細かく、正しく、わかりやすく、が重要です。 この3つのポイントを忘れずに作成すればスムーズな貿易取引が期待できます!