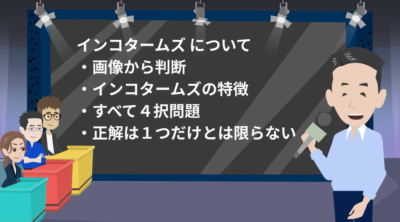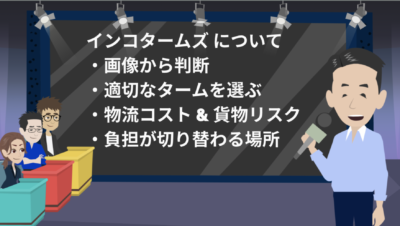
2021.01.30
第一回!物流クイズ-正しいインコタームズを当ててみよう!
第一回!物流クイズ どうも、こんにちは飯野です。さあ、始まりました新企画。物流クイズでございます。 このチャンネルではIt’s fun to learn Logistics「物流を学ぶのは実は楽しいことなんだ」というテーマでお送りしておりますので皆さんの物流や貿易の知識を是非 力試しして欲しいと思ったので 今回のクイズ企画を作りました。 楽しんで頂ければと思います。 まず簡単にクイズの概要を説明します。今回のクイズはインコタームズ についてです。 これから一枚ずつ画像が表示されます。この画像をみてEXWやFOBなど、どのタームかを当てるクイズです。 判断するポイントは輸出者と輸入者との間での「物流のコスト」と「貨物のリスク」の負担が切り替わる場所です。 全く分からないという方のために、関連動画集を概要欄に貼っておきますのでそちらを見てから挑戦してもらっても大丈夫です。では、いってみましょう! 第一問 問題。これはどのインコタームズを表しているでしょうか? A. DDP B. EXW C. FOB D. CIF 正解はBのEXWです!物流コストと貨物のリスクを輸出者の工場から全てBuyerである輸入者が負担するという図ですので、タームはEXWになります。 第二問 では続いての問題。これはどのインコタームズを表しているでしょうか? A. CIF B. DDP C. CFR D. FOB 正解はBのDDP!先ほどのEXWとは逆で、輸出側の工場から輸入側の届け先までSellerである輸出車が費用と貨物のリスクを全て負担すると表している図です。なのでタームはDDPになります。 第三問 問題。これはどのインコタームズを表しているでしょうか? A. FCA B. DAP C. DPU D. CFR これは少しトリッキーなタームですね。正解は。。。DのCFRです! 物流コストの負担は輸出者が輸入側の港まで負担する。そして貨物のリスク負担は輸出者が輸出側の港までを負担する条件です。 インコタームズのCグループはこのようにコスト負担とリスク負担が変わる場所が違うトリッキーなものなので注意が必要です。 第四問 続いての問題はこちら。これはどのインコタームズを表しているでしょうか? A. DAP B. CPT C. FOB D. DPU さて正解は。。CのFOBです!コストとリスク負担を輸出者は輸出側の港まで、それ以降を輸入者が全て負担するという取引条件です。FOBは貿易では頻繁に使用するタームです。 第五問 それでは最終問題です。この図は、コスト負担とリスク負担のどちらを表現しているでしょうか? 3択問題です。 A. コスト負担 B. リスク負担 C. どちらでもない さあ、ここで50:50. Cのどちらでもないが消えます。 ※みのもんた風のタメ 正解はAのコスト負担です! 問題の解説 もう一枚別の図を見て一緒に解説しましょう。この問題でのポイントはCFRとCIFです。先ほどの問題の左の図は輸出者が輸入側の港までを負担するもの。これは物流費用・コストでしたね。 そして右側の図では輸出者が輸出側の港までしか負担しない。これは貨物のリスクでした。 このトリッキーなタームをしっかりと理解しているかどうかが正解を分けるポイントになりましたね。 まとめ 今回の物流クイズはいかがだったでしょうか? 慣れている方には簡単なものだったかもしれません。 しかし貿易・物流の基本といえるインコタームズは確実に理解しておかなければいけません。 輸出者と輸入者で取引条件の共通認識が出来ていなければ勘違いが生じてトラブルの元になってしまいます。 これからも 楽しく学べる物流のクイズを作っていきますので 次回もお楽しみに!ありがとうございました! ・TwitterでDMを送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedInでメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/ お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。