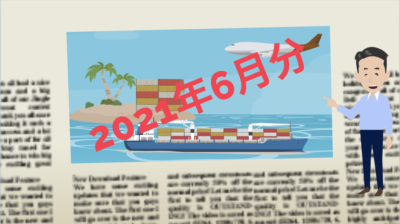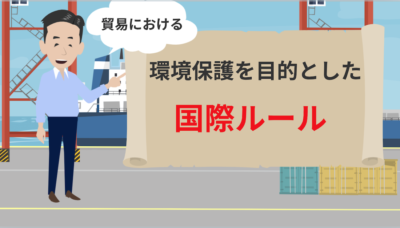2021.07.29
【フォワーダー2.0】デジタルフォワーダーの時代、中小企業の今後の戦い方。
フォワーダーのデジタル化が日本でもやっと進んできたような気がします。業界ではデジタルフォワーダーという名称のスタートアップがアメリカ、ヨーロッパ、中国で注目されていました。 私個人的に注目していたデジタルフォワーダーのスタートアップはアメリカのFlexport。最近では住友商事のVCが出資したという中国のYunquna。そして日本のデジタルフォワーダーの始祖 Shippioです。 これらのスタートアップの動きを見て、タイにある弊社グループでもデジタルフォワーダー化するべきだ!と2020年1月にグループミーティングで提案しました。現在はペンディング中です。理由は以下にて説明します。 そして、ここ最近日系の大手フォワーダーにデジタル化の動きが見えるようになってきました。 さすが日通。契約した船社のスペース・Booking・価格などの情報が社内にオンタイムで共有される。「確実」にスペース状況が分かるというのは昨今の海運ではマジで必要な要素。この一元管理は今後、通関やトラックにも広がっていくはず。物流業界が面白くなってきたぞ!https://t.co/khegnPiAl7 — イーノさん@物流会社の社長🇹🇭 (@iino_saan) July 20, 2021 予想通り大手フォワーダーから、どんどんデジタル化が進んでいくよね。中小フォワーダーとして生き残り戦略を考えないと。 【コンテナ】三菱商事ロジ、船腹予約の新PF稼働。貨物動静確認まで一元管理 https://t.co/qkuJss4d8M — イーノさん@物流会社の社長🇹🇭 (@iino_saan) July 22, 2021 タイトルで「フォワーダー2.0」と流行りの〇〇2.0を使ってしまいましたが、フォワーダーも遂に新しいステージに行くタイミングだと思ったので考察を書いていこうと思います。 デジタルフォワーダーとは? デジタルフォワーダーという言葉に馴染みがない方の為に簡単にご説明します。デジタルフォワーダーとは、独自のITプラットフォーム(PF)を使い、見積もりの即時提出、荷主からのBooking、貨物のトラッキングを一元管理しているフォワーダーです。 簡単にこれまでのフォワーダーと比較をしてみましょう。 従来のフォワーダー ・見積もり:都度確認、メールや見積書にて提出 ・Booking:メールでBookingを受付 ・トラッキング:営業やカスタマーサービスが調べて連絡 デジタルフォワーダー ・見積もり:PFで表示 ・Booking:PFで受付 ・トラッキング:PFで表示 このようにプラットフォーム(PF)で一元管理され、簡単に必要な情報にアクセス出来る仕様です。 見積もり、Booking、トラッキングは現時点での主要な機能ですが、今後は更にサービスが広がっていくと思います。 その他の機能(一部は未来予測) ・B/Lの間違いチェック*S.I、INV、PKLからAIで間違い探し ・eB/L(制度改正が必要) ・本船の残りスペースの表示 ・各港の混雑状況の表示(沖待ち日数) ・写真をアップロード -> HS Codeの表示 ・HS Codeを入力して必要書類(他法令)の表示 ・HS Codeを入力して配送可能(主にDG)か事前確認 ・輸入関税・消費税金額の自動算出 ・Arrival Noticeの電子送付 ・D/OのQRコード化 ・輸入申告のオンタイム状況の表示 ・フリータイム切れまでのカウントダウン ・デマレージ費用のオンタイム表示 ・配送先の住所を入力してトラック費用の算出 などなど。AIとブロックチェーンなどの技術も使って、技術的には全て出来る内容だと思います。 これまでデジタル化が進まなかった原因 物流のお仕事に従事されている方なら、上記のような便利なツールや機能があったらいいなと思うのではないでしょうか。他の業種では既に使われている技術なのに、なぜ物流業界ではデジタル化が進まなかったのか? これは ・物流業界の人たちの考えが古すぎる(コンサバ) ・業務プロセスが多く、関係各社が分かれている この2つが主要な問題です。 弊社でもプラットフォームを導入するにあたり、全体会議を何度もやりましたが つまづいたのは上記の理由です。 致命的問題:関連業社が多すぎる件 コンサバは時間が解決してくれると信じているのですが、もう一つの問題が厄介です。 私たちフォワーダーは(特に中小企業は)基本的にはアセット(自社の設備)を持たないケースが多いです。なので船・飛行機を含め、通関、トラック、倉庫などを複数の業者に外注しています。 各社で使っているシステムが違う 現在ではそれぞれの業者・会社が自社の都合の良いようにシステムを導入しています。システムがないと膨大な物流手配の情報は取り扱えないのですが、このシステムが足枷となります。 1件の輸送をする為の関係各社のシステムが違うので、フォワーダーのプラットフォームと各社のシステムとの連携が①技術的、②権利的に難しいのです。特に後者②が深刻だと思ってます。 システム業者からしたら、「なんでそんなプラットフォームと連携しないといけないの?」となります。実際に弊社のプラットフォーム開発ではここで止まりました。 IT企業あるある このように各社のシステムが違うのに、現存のデジタルフォワーダーはプラットフォームどのように一元管理をしているのでしょうか? これは私たちもプラットフォームを作ろうとしたので分かりますが、表向きはIT開発をしているけれども、運用は人がやる仕組みになってしまいます。 現在、船会社はBookingを各自社Webサイトで受け付けていて、トラック会社はメール(またはFAX)でのBooking受付が殆どです。 なので ・フォワーダーのプラットフォームでBookingを受ける ->自動で各船会社・航空会社のWebサイトへBookingする ->自動でトラック会社へメールでBookingする このようなシステムは技術的には出来なくないと思いますが、小額投資しか出来ない弊社だとそれは無理でした。自動で出来ないので、人が泥臭くBookingやキャンセル手配をすることになります。 大手企業はトップの鶴の一声か? 私自身が大手フォワーダーの内部にいるわけではないので勝手な想像なのですが、冒頭で紹介した日通や三菱ロジでは、トップが「デジタル化するぞ!」と言ったら、関連会社のシステムも合わせられると思ってます。 大手は自社でアセットも持っているので、それに合わせたプラットフォームも開発がしやすいんですよね。そういう意味で大手企業ほどコンサバかと思っていますが、やるときはパワーを使って変えられる強みだと思います。 大手フォワーダーがデジタル化する脅威 デジタルフォワーダーというスタートアップが出て来て、いきなり市場が取れる程 この国際物流業界は甘くありません。確かにプラットフォームは便利ですし、これからはトレンドがきて、今後は一般化するでしょう。 しかし貨物を海外に運ぶというフォワーダーの仕事においての前提条件は、貨物を運べるスペースをしっかりと持っていることです。取り扱いスペースがなければ、見積もり・Booking・トラッキングをいくら便利にしても、そもそも運べません。 冒頭に紹介した日通は日本No.1フォワーダーの購買力を生かし、複数の船会社とスペースを契約。そのスペース状況をオンタイムで内部に共有しているとあります。 2022年下旬まで購買を制すものが有利 この記事を書いている現在はコロナによるコンテナ不足、本船のスペース不足の為に海上運賃が過去最高に高騰しています。特にアジアからアメリカやヨーロッパ向けなどは、貨物を送りたくても送れない状況が続いています。 こちらの記事でも書きましたが、現在はフォワーダーの二極化が始まっています。 [keni-linkcard url="http://forwarder-university.com/selected-forwarder/?lang=ja" target="_blank"] スペースが取れるフォワーダーはキャリア(船会社・航空会社)と共に収益を上げ、スペースが全く取れない会社は残念ながら仕事が取れません。 このコンテナ不足、スペース不足はいつになったら解消するのか?という話題はよく聞きます。現状からすると年内までは続くという見方が強まって来ました。 また2022年7月1日にアメリカ西海岸の労働組合の労働協約が失効するので、また北米西海岸で一悶着があり、コンテナの目詰まりが発生するでしょう。全くスペースが取れないことはないと思いますが、タイトな状態になる可能性は十分にあります。 中小フォワーダーはどうやって対抗すべきか? このような市場の状態において、中小フォワーダーはこれからどのようになっていくのでしょうか?結論を言いますと、従来のアナログで海上輸送・航空輸送のみを対応するフォワーダー1.0は淘汰されます。 すぐにではないでしょうが、全ての大手フォワーダーがデジタル化を完了させて攻め込まれると、中小のアナログフォワーダーは勝てません。 テクノロジー化が進むにつれてコストは下がります。更に大手は強い購買力でスペースが取れますし、物流管理をデジタル化することで人件費も下げられます。 中小フォワーダーの救世主が現れるか? このように書くと、自社でシステム開発をしなければいけない!莫大なコストがかかる!と心配になったかもしれませんね。大丈夫です、ご安心ください。 上述しましたが弊社でもデジタル化を進めようとしたくらいなので、他の中小フォワーダーでもデジタルプラットフォームを採用することは可能です。 実はフォワーダー用のプラットフォームを開発してくれる会社があります。また今後はサブスク(月額課金)でプラットフォームを使わせてくれる会社も増えてくるとも思います。 世界各地でトータル・ロジスティクスすべし プラットフォームを導入すれば大丈夫か?というと、そうではありません。プラットフォームはこれからの必要最低条件です。 プラットフォームが出来たことで、価格に透明性が生まれます。船会社・航空会社の代理店業としてスペースのみを販売していたフォワーダーは、この価格のガラス張りで「利ざや」が抜けなくなるのです。 デジタル化が進むことで簡単に価格が比較され、多くの場合で選ばれるのが最も安く貨物を運んでくれる会社。または適度な価格でワンストップ・サービスしてくれる会社です。 国際物流は海上・航空輸送だけではありません。その前後の陸送、通関、梱包など、また貨物によって運び方も変える必要があったりします。 海外の代理店との連携を強化する 更にいうと、トータルロジスティクス(ワンストップ)だけでは生き残れません。大手企業ももちろんトータルでサービスを提供して来ますし、ここでポイントになってくるのが 海外の支店・代理店の存在です。 国際物流は2国間で貨物輸送手配をします。そして大手企業は海外に自社の支店を持っていることが多いですが、それが足枷になるケースもあります。 海外に支店があるのと、海外の支店のサービスが良いは全く別の話。 これは大手フォワーダーに勤めていた人から聞いた話ですが、海外の支店のサービスが悪かろうと、そこを使わなければいけない縛りがあるそうです。 中小フォワーダーの場合は各地に支店がなく、ローカルのフォワーダーと代理店契約をしている場合も多いと思います。そして、そのなかで良い代理店を選べるというのが逆に強みだったりします。 まとめ やっとこの国際物流業界でも空気が変わって来ました。技術的には出来そうなのに 構造上の問題でなかなか進まなかったデジタル化。これがDXというトレンドワードによって、このコンサバ業界が動き始めたのです。 ここで変われない会社は間違いなく淘汰されます。弊社グループでもまだ変われていないので、個人的にこのまま行くとヤバいと感じていますが、大切なのは変わろうとする意思と行動。 もしデジタル化に時間がかかったとしても、中小フォワーダーと関連業者による強い連携があれば大手企業とも戦っていけると思っています。 さぁ、フォワーダー2.0に向かって動き出そう。 追伸 変わる必要なんてない!今後フォワーダー業界は安泰だ!と楽観している方のために、こちらの動画をご紹介します。 日本の海運の歴史を解説した動画ですが、かつては日本の船会社は12社ありました。現在の邦船社は3社(日本郵船・商船三井・川崎汽船)。コンテナ事業は1社(ONE)に統一されました。