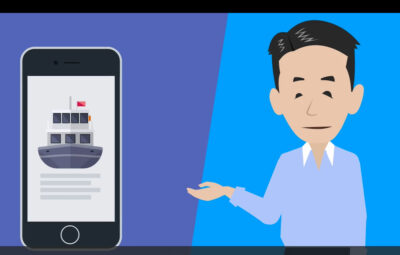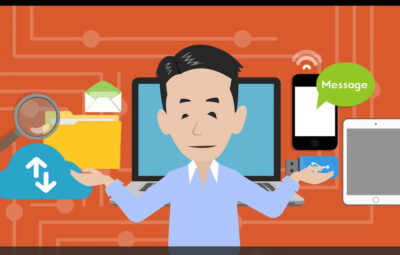2021.05.19
2021年4月 物流ニュース
2021年4月 物流ニュースを動画で見る どうもこんにちは飯野です。 今回は新しい取り組みとして、最近にあった物流・海運に関するニュースをまとめて私の動画でもっとカジュアルに伝えようと思いました。 物流業界で働く人も、そうでない人も楽しく物流の今に触れて頂ければと思います。 では、いってみましょう。 世界の貿易量、すでにコロナ前に回復 オランダ経済政策分析局によると世界貿易量は2月時点で、すでに新型コロナウイルス禍の前の水準を上回っているとの発表がありました。 コロナ禍でいったん落ち込んだ分の挽回である、「ペントアップ」需要が押し上げており、これをけん引しているのは米国と中国になります。 昨年春にはコロナ禍で世界中で需要が冷え込み、生産調整が進みました。 しかし経済活動の再開とともに、先送りされた消費が戻っただけでなく、在庫を回復させる動きが活発になり、生産や貿易が一気に上向いています。 コロナ禍からの立ち直りが早かったのは中国。1~3月は輸出入ともに過去最高を記録。 また米国も中国などアジアからの輸入を大きく増やしています。日本海事センターによると、アジア18カ国・地域から、米国へのコンテナ輸送は2020年は過去最高とのこと。 このうち、2割強を占めるのが家具・家財道具や、建築用具といった住宅関連です。 米国の住宅市場は低金利環境に加え、コロナ禍による郊外への移転などが重なり活況を呈(てい)しています。 住宅着工が増えるにつれ、米国の関連資材の需要が増え、更に「巣ごもり」による電化製品などの需要拡大も、コンテナ輸送の増加につながっています。 北米西岸港湾、貨物急増でパンク寸前。 アジア発 アメリカ向けコンテナ航路の荷動きが記録的な水準で推移する中、北米港湾や内陸輸送がパンク寸前となっています。 LAやLBなどの港湾ではターミナル内の混雑が悪化して貨物が滞留しており、鉄道への接続も滞るなど、混雑状況は悪化しています。西岸経由の機能不全で東岸サービスの引き合いも急増しており、新規ブッキングはまったく入らないなど、混乱が広がっています。 船社関係者によると、「アジア発を含めて5月中のスポット貨物の新規ブッキングはまず無理」とのこと。 アジア発、北米東岸向けスポット運賃の実勢レートは、40フィートコンテナ1本当たり1万ドルまで上昇しています。 国際海運、「2050年までに温室効果ガスゼロ」。脱炭素化さらに加速へ。 続いてのニュースです。 4月21日に開かれた、気候変動サミットへに向けての特別会合で、10カ国の代表者により国際海運の温暖化対策について、意見交換がありました。 この中でアメリカのジョン・ケリー特使は、国際海運からの温室効果ガス排出量を2050年までにゼロにするという野心的な目標を提言。 IMO(国際海事機関)の温室効果ガス削減戦略を上回る目標が提示されたことで、国際海運における脱炭素化がさらに加速しそうです。 この目標に対して、関係者からは「環境技術の研究開発に弾みがつく可能性もある」との声も上がっています。 アメリカ、ドライバーの需要が急増。賃上げ実施しドライバー確保へ。 ここからはアメリカからのニュースです。 米国のトラック会社は、需要が急増しているドライバーを確保するため、賃金を引き上げました。 米国のトラック運送会社は、消費者の需要が急増し輸送能力が逼迫(ひっぱく)していることから、貨物市場の復活に向けてドライバーの増員に躍起になっています。 実際に賃上げを行った、業界大手のKnight-Swift Transportation Holdings(社) INCは資格を取得したばかりのドライバーの賃金が、ここ数カ月で40%以上も上昇したと報告。 労働統計局によると、昨年の大型トラックおよびトラクター・トレーラのドライバーの給与の中央値は4万7,130ドルでしたが、同社によると免許を取ったばかりの教習後1年目のドライバーでも、年収6万ドル以上を稼げるようになったと伝えています。 TuSmple社 IPO トラックの自動運転にも注目が集まっています。米国と中国に拠点を持つTuSimple社は、4月12日 新規株式公開を行い約3,380万株を販売して10億8,000万ドルを調達しました。 同社の関係者によると、今年、第4四半期にツーソンとフェニックスを結ぶ約100マイルの距離で誰も運転しない「ドライバーアウト」のパイロットプログラムを実施する予定であると述べました。 このパイロットプログラムでは顧客の貨物を輸送する予定で、アリゾナ州の運輸当局と緊密に連携して調整を進めているとのこと。 同社は新技術の開発を進め、最初の商業収益を2024年と予測しています。 解説コーナー それでは本日のニュースの解説のコーナーです。 まず最初のニュースですけれども、アメリカ向けの輸送が本当に伸びていますよね。中国からの輸送も過去最高と、アメリカの人たちの巣ごもりの消費って本当にすごいなと思います。 コロナのワクチン接種も進んでいますし、経済活動はこれからも伸びそうですよね。 これまでは港湾やトラックドライバーもコロナで稼働が制限されていたので、荷役のスピードやドライバー不足などはあったりしましたが、アメリカのトラック会社も賃金アップなどをしてドライバーを確保しようとしています。 私の個人的な予想ですが、インフラの回復より物量の増加の方が多くて まだまだ物流は安定しないかなと思っています。 また将来的にですがトラックの自動運転が一般的に普及されることで今回のコロナで発生したようなドライバー不足は無くなっていくので、今後の技術の進歩にも注目ですよね。 最後にですが、アメリカが主催した気候変動サミットが4月24日に閉幕したのですが、これが関係してか海運業でも温室効果ガス削減への取り組みのニュースを最近多く見かけます。 船の燃料を液化天然ガスにしたり、アンモニアを使ったり、風力も使おうとしたり、スクラバーがデフォルトになっていたりと各関係会社で技術開発が進められています。 これに関しても非常に面白いコンテンツだと思いますので、今後も注目して取り上げていきたいと思います。 今回の物流ニュースはいかがだったでしょうか。一般的には海運のニュースって業界の人しか見ない印象ですが、こんな感じでカジュアルに、ニュースも発信していきたいと思います。 今回 参考にしたニュースのソースは以下にリンクを貼っておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。 現場からは以上でーす!ありがとうございました!! 2021年4月物流ニュース - 参照情報 快走する海運株 世界貿易量、すでにコロナ前回復 北米西岸港湾、貨物急増でパンク寸前。滞留悪化、内陸受託停止も 国際海運、「2050年までにGHGゼロ」。脱炭素化さらに加速へ。ケリー米特使が提言 Trucking Companies Boost Pay in Hunt for Drivers as Demand Surges Autonomous-Truck Developer TuSimple Plans Driverless Road Test This Year ・Twitter で DM を送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedIn でメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/ お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。