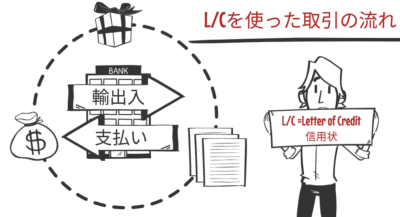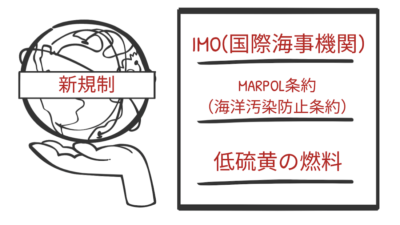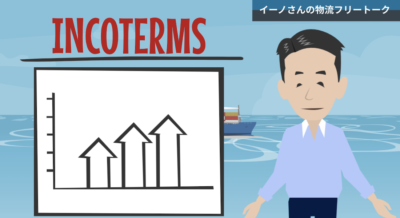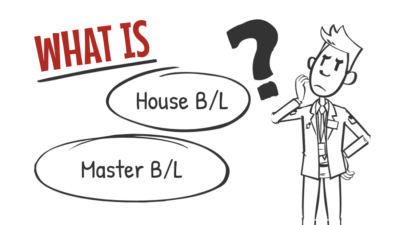2020.11.28
フリータイムとディテンションの違い
フリータイムとディテンションを動画で解説 今回はフリータイムとディテンションの違いについてご説明をしたいと思います。 コンテナを使った海上輸送をしているとフリータイムという言葉を頻繁に使います。 フリータイムとディテンションとは フリータイムとは、港でのコンテナの無料保管期間のことです。 予め決められたフリータイムの期間は、コンテナを港に無料で置いておくことができます。 そして、このフリータイムと合わせて覚えておかなければいけない言葉があります。それは、デマレージとディテンションです。それでは詳しく見ていきましょう。 フリータイムについて まずフリータイムについてです。 フリータイムは港で無料でコンテナを保管できる期間のことで Dryコンテナなら一般的に7日〜14日です。 この期間はフォワーダーによっては延長のリクエストが可能です。 弊社の場合だと日本の主要港向けだと最大21日までフリータイムを延長できる場合があります。 このフリータイムですが船会社によって長さが違います。 なので貨物のBooking時にフォワーダーにフリータイムの期間を確認をしておきましょう。 そして注意しておきたいのはリーファーコンテナや、オープントップ、フラットラック コンテナの場合はフリータイムは短くなります。大体 1週間未満です。これも事前に確認をしておきましょう。 コンテナが港についたら早く取り出した方がいいんじゃないか?と思われるかもしれません。 しかしフリータイムはこんな状況でよく利用されます。 ・通関に時間がかかる ・工場に貨物を置くスペースがない ・ドレージの手配に時間がかかる 基本的に港は倉庫ではないので問題がなければ速やかに貨物を取り出さないといけないのですが 一般的にはこのような理由でフリータイムが活用されることが多いです。 デマレージについて そしてデマレージについてご説明をします。 デマレージはフリータイム期間が過ぎてしまってから発生する超過保管料金のことです。 先ほどもお伝えしましたが港は倉庫ではありませんしコンテナヤードのスペースにも限りがあります。コンテナをずっと港に保管しておくことはできないのでこのような超過料金が発生します。 このデマレージの金額ですが安くありません。 ある船社での例ですが、1日目から3日目までは40’feetコンテナ1本あたり、1日で13,000円かかります。 そして4日目から6日目は1日1本あたり25,000円、7日目以降は変更しないのですが1日1本あたり40,000円となります。このように超過期間が長くなるにつれて,金額が加算されていく仕組みになっています。 もし1shipmentのコンテナが10本だとしたら、 かなりの金額になってしまいます。 ディテンションについて 次にディテンションについてご説明します。 ディテンションとはコンテナを港から引き取り、貨物を積み下ろしして、空コンテナをまた港に戻すまでの期間のことです。 この期間を過ぎてしまうと費用が発生します。コンテナは船会社の所有物ですので使い終わったら、ちゃんと返却する為の仕組みです。 フリータイムとディテンションの起算方法についても例を上げて解説します。 例えば、フリータイムが14日間、ディテンションが7日間だったとします。本船が港に到着するETAが5月1日で、コンテナが船から積み下ろされてコンテナヤードに搬入されるのが5月3日としましょう。 この場合、フリータイムは5月17日までとなります。搬入日から起算する場合もあれば、国によってはETAから起算するところもありますので事前に確認をして下さい。 そして、コンテナをフリータイム最終日の5月17日に引き取りに行ったとしましょう。 ディテンションはコンテナ引き取り日から起算しますので5月24日までとなります。 実務ではディテンションを最大まで使うというケースは稀ですが、このようになります。 フリータイムでよくある問題 最後にフリータイムでよくある問題についてご紹介します。 それは通関がフリータイム中に完了しないという場合です。 特に新しく取り扱う商品を輸入する場合、新商品は輸入実績がないため必要書類を見落としている可能性があります。 食品や化学品など輸入する為に許可登録が完了していないと輸入できない貨物も沢山あり、登録には大抵時間がかかってしまいます。 他にもB/Lにミスがあり修正に時間がかかってデマレージが発生する場合もあります。 そうならない為には、新商品の場合は貨物を輸出する前にフォワーダーに相談をしてちゃんと準備をすること。 B/Lなどの書類ミスには注意することを忘れてはいけません。 まとめ いかがだったでしょうか。 今回の説明でフリータイム、ディテンション 、デマレージという専門用語は理解できたと思います。ですが大切なのはフリータイムを上手に使いデマレージを発生させないという実務上での注意です。 私もフォワーダーを長年やっていますが 商品の登録や書類のミス、売り手買い手側での支払い問題、長期休暇後による港の混雑などで フリータイムが切れてデマレージが発生するケースは沢山見てきました。 フリータイムは国際物流の実務において特に注意しなければいけないポイントですので 実務では事前確認などしっかりとして、準備をしましょう。 ・TwitterでDMを送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedInでメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/