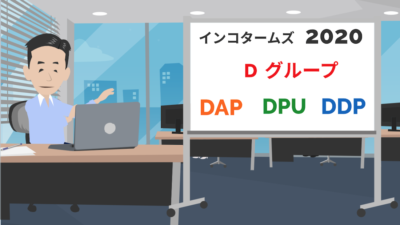2022.01.19
なぜ日本の物流業界では給料が低いのか?
どうもこんにちは、飯野です。 今日は、「なぜ日本の物流業界では給料が低いのか?」というテーマでお話していきたいと思います。 2022年1月19日イーノさんの物流ラジオ 物流業界の給料 昨日、拓殖大学の松田先生とお話しをした中で、「なぜ物流業界の給料が低いのか?」という話題が上がりました。 北米だとトラックドライバーの給料はなりたての人でも800万円ほどで、1,000万円オーバーのドライバーも結構いると記事を見たことがあります。 ちなみに北米西岸の港湾労働者の年収は2,000万円くらいですが、今年7月には労働協約が失効しますので、更に給与の交渉が始まりまるでしょう。 では、なぜ日本は低いのでしょうか。 業務の効率化が必要 僕の仮説ですが、物流業界はITや金融に比べて、一人当たりが生み出す価値の総額が低いと思います。 輸送費用は、コストとして叩かれがちです。 輸送費用を高く取れるのは、今の船会社・航空会社であり、フォワーダーなどはマーケットが決まっているため、なかなかあげることができません。 しかし、郵船が今期、売り上げ一兆円を超えで話題になっています。僕の知っている船会社のマネージャーは現在、毎月350万円もらっていますが、日本のONEの人はこんほどもらっているのでしょうか。 まず、会社が効率的に儲かっていなければ、従業員の給料は上がりません。 高い給料をもらえる条件として、下記2点が考えられます。 ・会社自体が儲かっていること ・効率が良いこと 松田先生との会話で、物流業界は人数が多いという話になりました。実際、一人が抱えている業務量はそれほど多くはないと感じます。 そのため、一人当たりの給料を上げることが難しいのではないでしょうか。 また、現場で働いていても物流業界は非効率だと思います。 フォワーディングだけやっているのであれば、まだ効率的ではありますが、その前後のトラック・通関も行うと非効率になってしまいます。 実務では、ブッキング依頼があると、お客様へ複数の提案をし、いただいた回答に合わせてスケジュールを調整し、動きます。 しかし、キャンセルになった場合は、また一からトラックなどを取り直ししなければなりません。 DX化の必要性 先日もお話しましたが、物流のDXが進めばもっと効率的になります。 よって、給料を上げるためにはデジタル化は必須です。社内の効率が上がれば、将来的には物流業界の給料も上がっていくはずです。 しかし気をつけないといけないのは、仕事がなくなることです。 テクノロジーにとって変わられる仕事のみをしていると、仕事がなくなってしまいます。 それに対してどのように対応していけばいいのか、という問題に関してはまた別の機会にお話をしたいと思います。