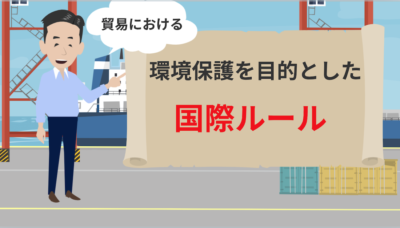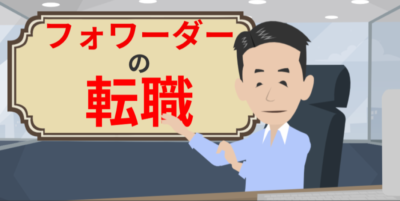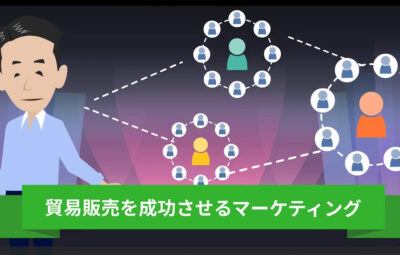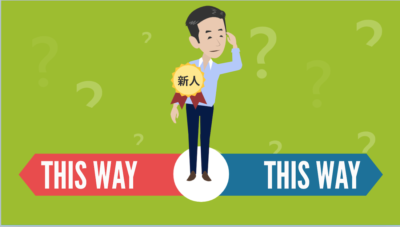2021.08.02
フォワーダーに見積もり依頼するときの必要情報
どうもこんにちは飯野です。 今回は「フォワーダーに見積もり依頼をする時の必要事項とその理由」というテーマでお話をしていきたいと思います。 おかげさまで私のYouTube動画やブログを見て頂いた方から、国際輸送の見積もり依頼を頂くケースが本当に多くなりました。ありがとうございます! ですが、中には貿易に慣れていない方からの見積もり依頼もあり、必要情報の確認に手間取る場合があります。これを機会に動画でちゃんと説明をした方がいいなと思いました。 今回の内容を紹介することで、慣れていない荷主さんはよりスムーズで正確な費用確認が出来ることになると思います。それにより問い合わせを受けたフォワーダーさんの確認業務の削減に繋がるかとも思います。 それではポイントを紹介していましょう。 フォワーダーが困る見積もり依頼とは? まずですが、私たちフォワーダーにとって困る見積もり依頼について内容をご紹介させて頂きます。弊社の問い合わせでは、こんな感じのシンプルなメールが送られてきます。 ・タイから中国まで 海上輸送でいくらかかりますか? ・タイからマレーシアまでトラックでいくらかかりますか? これを見て何が足りないの?と思われた方。申し訳ありませんが想像力が足りていません。 積み地、揚げ地の港・空港名 貿易取引をするためには輸送費用を含めコスト算出が不可欠ですよね。マーケティングで市場調査をしている段階で ざっくりした費用確認の場合だとしても、タイから中国だと範囲が広すぎます。 輸出する国と、輸入する国の具体的な港や空港の名前が必要です。日本語では積み地、揚げ地と呼びます。 貨物の引き取り先、配送先の住所 またクロスボーダートラック輸送の場合はDoor to Doorのケースが多いので、タイからマレーシアという輸送条件で見積もり依頼がきても、タイとマレーシアのどこからどこまでですか?と思ってしまいます。 貨物の引き取りと、送り先の具体的な住所が必要になります。 貨物内容 貨物内容が書かれていないと、何を送るかも私たちは分かりません。貨物内容によっては輸送方法が異なってきます。 例えば精密機器を送るのと、冷凍マンゴーを送るのでは全く条件が違いますよね。 また貨物が危険品だとしたら、見積もり手配以前に そもそも運べるのかどうかも確認する必要があります。 貨物サイズと重量 貨物のサイズと重量も大切です。1パレットの貨物を送るのと、コンテナ10本以上が必要になる工場のプラント設備一式送るのでは全く違います。 また綿のように軽いけどかさばるもの、鉄のロールのようにスペースを取らないけど、ものすごく重たいものを運ぶ場合も計算方法が異なります。 貨物の梱包形態 梱包形態も教えて欲しいです。貨物がカートンのバラ積みなのか、パレット梱包なのか、荷姿がドラムやフレコンバッグなのかも分かると助かります。 例えば新品の機械で全く梱包されていない状態だと、海上輸送中に動いてダメージにつながる為、安全に輸送するためには梱包の提案をする必要が出てきますので。 インコタームズ B2Bの輸送ではインコタームズも必要です。EXWだと分かればピックアップ住所の情報が必要になるし、DDPであれば配送先の情報も必要になります。 輸出でFOB費用が必要だと、フォワーダーは国内輸送費だけを確認しますし、これがCFRだと海上運賃も含めた費用の確認になります。 インコタームズについて詳しくは再生リストにまとめていますので、そちらをご確認頂ければと思います。 配送頻度 最後に輸送頻度もあると嬉しいです。毎月1本と毎月10本のコンテナ輸送では取り扱い量が違いますし、ボリュームが多ければ船会社や航空会社への価格交渉もしやすくなります。 また見積もりは営業マンの匙加減にもよりますので、ボリュームが多くて確実に取りたいと思う営業マンは安く提案してくれる場合もあります。 まとめ それでは、フォワーダーが見積もり手配に必要な情報をまとめます。 ・貨物内容 ・輸送形態(航空輸送、海上輸送、トラック輸送など) ・インコタームズ ・引取先の住所(タームによる) ・積み地(港・空港) ・揚げ地(港・空港) ・配送先の住所(タームによる) ・梱包形態 ・貨物サイズ ・貨物重量 ・配送頻度 これらの情報があると完璧です。見積もり手配はスムーズになりますので、項目をメモして頂ければと思います。 慣れている方であれば状況に応じて必要最低限の情報をご連絡頂けるかと思いますが、より詳しい情報を頂ければ その分 回答する見積もりの内容や精度もあがります。 今回お話しさせてもらった内容が、よりスムーズな見積もり依頼や手配につながれば幸いです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました! ・Twitter で DM を送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedIn でメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/ お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。