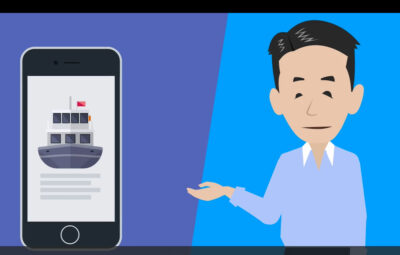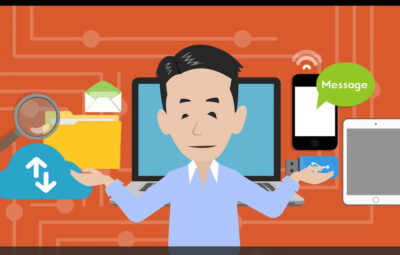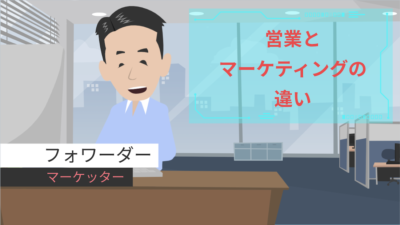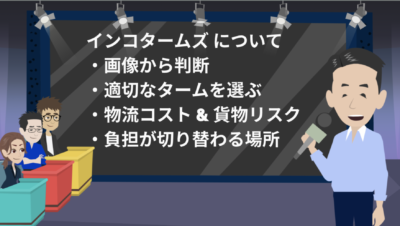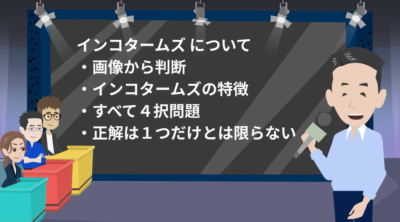日本の近代海運の歴史と今後の課題について動画で解説
どうもこんにちは、飯野です。
今回は日本の近代海運の歴史と今後の課題というテーマでお話をしていきたいと思います。
菅哲賢社長の著書「最適物流の科学」
今回の動画を作るにあたり、参考にした本があります。
それは、ジャパントラスト株式会社 菅 哲賢(てつまさ)社長の著書「最適物流の科学」です。
ジャパントラストさんは弊社の日本の代理店で菅社長は私ととても考えが似ている感じで、この本の内容も共感できるところが多かったです。
この本には日本の国際物流の歴史やフォワーダーとしての在り方、フォワーダーの選び方なども書いてあって
私にとっても非常に勉強になる本だったのでお勧めです。
それでは、本題にいってみましょう!
海運なくして日本の経済なし
ご存知の通り日本は島国です。
そして日本は全てを自給自足しているわけではなく、外国との貿易によって生活に必要なものや工業製品などを輸出入しています。
特に天然資源に関しては99%を輸入していて「海運なくして日本の経済なし」と言えるほど
海運とは切っては切れない地理的な特徴があります。
日本の海運を切り拓いた2社
日本の近代海運で有名人、というと誰を思い浮かべますか?
私は「岩崎彌太郎さん」を最初にイメージしてしまいます。
この方が1885年に日本郵船という船会社を設立し、今でもこの会社は世界中に支店があり、日本の海運を支えています。
郵船ロジスティックスというフォワーダーや倉庫など、総合的な物流でも有名ですね。
そしてもう一社 当時の日本の海運を切り拓いた会社がありまして、それが大阪商船会社。今でいう商船三井の最初会社です。
この2社が日本当初の、遠洋定期船を運行して、インド、欧州、北米、南米、豪州、台湾などとの貿易の架け橋となっていました。
近代海運の成長
これらの会社が近代日本史において成長したのは、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦です。
ロジスティックスという言葉は「兵站」と呼ばれる軍事用語です。
戦争による物資の輸送で日本は海運大国になりましたが、第二次世界大戦では軍用船だけでなく商船も戦争に使われ、約2千数百隻という船が失いました。
またゼロからのスタートになったわけです。
スエズブーム
戦後に少しずつ日本の船会社は経営を立て直していき、大きなきっかけとなった要因がスエズ運河です。
1956年にエジプトの当時の大統領がスエズ運河の領有を宣言しました。
この時に利権を巡って、エジプト、イスラエル、イギリス、フランスと対立が激化して、第二次中東戦争が勃発。スエズ運河が閉鎖されました。
これにより、大量の船が南アフリカの喜望峰回りを余儀なくされたんです。
すごい遠回りをしないといけないんですね。
世界中で船舶の絶対数が足りなくなり、海運市況は暴騰しました。
いわゆる、スエズブームです。このブームにより不定期船の運賃は約2倍となり
日本にとっても海運業界は第二次世界大戦後で初めての好況になりました。
しかし、スエズ運河が元通りに開通しますよ、ということで、このブームはたった1年で終わります。
そして更に悪いことにブームの反動もありました。
この時に船舶を作りすぎて供給過多になり海運業界は大不況となります。
海運業界の不況
日本の海運会社も経営悪化し、当時12社あった日本の船会社は、買収や合併を繰り返して、最終的に
・日本郵船
・川崎汽船
・大阪商船三井船舶
・ジャパンライン
・山下新日本汽船
・昭和海運
の6社に集約されました。
スエズブームの後 海運業界は不況でしたが、日本は歴史でも勉強した通り、戦後の複数の好景気を経て、高度経済成長をしていきます。
当時の為替は1ドル360円もして、輸出に非常に有利な状況でした。
しかし、ここから日本の海運業界にとっては、またも厳しい状況に経済は変わっていきます。
為替による更なる不況
当時の為替は固定相場制でした。1ドルが360円くらいで固定されていたら、日本の輸出にとっては有利な状態が続きます。
しかし1973年に固定為替相場制から変動為替相場制に移行します。
そして第一次オイルショック。燃料費の高騰と世界的な不況となります。
更に1985年の「プラザ合意」でドル高が是正されて、当時240円/ドル から約120円/ドルになり一気に円高になりました。
海上運賃はドル建てがほとんどです。
円高になると円での収入が減ってしまいますし、輸出製品の競争力がなくなって輸出する貨物が減ってしまいます。
1980年代は日本経済はバブルでしたが、日本の海運会社にとっては実は不況だったんです。
このような状況で、生き残るべく日本の各船会社は、撤退や吸収合併をしながら、6社に集約されていたものが
1990年代に日本郵船、川崎汽船、商船三井の3社となりました。
経済的な世界の海運市場
次に経済・経営的な視点から世界の海運市場について説明をしてきます。
海運業界は不景気だったんですが、世界的にコンテナ貨物の輸送量は増加をしています。
グローバル化に伴う国際分業が発展していったからです。
例えばアメリカのAppleのiPhoneの部品は各国で作られいますし、最終的には台湾のホンハイという会社で組み立てられています。
どれくらいコンテナの輸送量が増えていたかというと
2004年〜2014年の10年間で、日本を除くアジアではコンテナ輸送量は約2.2倍増えています。
一方で日本はというと約1.3倍で増えてはいるが、他国に比べるとそれほど大きな伸び率ではありません。
世界的に荷動きの量が増加してるんだったら、何で船会社は不景気なの?と思われる方もいると思います。
それは、船の「巨大化」が原因となっています。
近年の船は巨大化しており、大きい船だと20,000TEUといった、20feetコンテナなら2万個を一度に運ぶことが出来ます。
船会社は船のサイズアップをすることで輸送の合理化を進めていき、コストダウンを図ろうとしたんです。
しかし貨物の実際の輸送量より、運べるスペースの方が多くなり、供給過多になってしまいました。
船会社は船の輸送スペースを在庫することは出来ません。
なので、一度の航海で出来る限り船のスペースをいっぱいにしないと、船会社は赤字の状態で船を運行することになります。
この船の巨大化が要因の一つで、世界の船会社は各国で競争が激化していきます。
現在はコロナによってコンテナ不足が発生して、海上運賃の高騰が激しいんですが、
それよりも以前では、海上運賃はずーっと底値をキープしていました。
日本からタイの輸送でも40feetコンテナで200ドルしない金額でした。
2016年に韓国の大手船会社が倒産したのも、この激しい価格競争による、ずっと長く続いていた低価格運賃が原因でしょう。
この強烈な価格競争に生き残るべく、海運業界では世界的な規模で、船会社の買収が繰り広げられました。
日本の船会社もそれに負けじと、日本郵船、川崎汽船、商船三井の3社でコンテナ事業が1つに統合され
2017年にONE(オーシャンネットワークエクスプレス ホールディングス)として設立されています。
安い日本の海運マーケット
そして意外かもしれませんが、近年の日本の海運マーケットは世界一安いとも言われていました。
これは船会社と実荷主の直接契約の歴史が長いのも、原因の一つだと考えられています。
これまでは船会社が荷主に運賃を提示する際に、
・大手荷主だから
・有名荷主だから
・付き合いが長いから
といった非経済的な理由で安売りをしていたケースもあったんです。
コンテナ不足
このような安いマーケットプライスの日本の海運業界ですが、現在、起こっていることは何だと思いますか?
「日本にコンテナが集まらない」です。
他の動画でも解説をしていますが、現在のマーケットではコロナウィルスによる世界的なコンテナ不足が発生しています。
これまでに説明したように、ずっと不況で赤字経営を続けていた船会社は、このタイミングで運賃を上げて一気に黒字に持っていっています。
船会社にしてみると収益性が低い日本にコンテナを集めるより、収益性の高い中国から北米、欧州へのロングホールにコンテナを集める方が儲かります。
多分 多くの方が今回説明したような海運業界のことを知らなかったと思いますし、
これまで不況を経験してきた船会社の状況を考えると、分からなくもない経営判断だと思います。
とはいえ、これは問題です。
現在では日本のコンテナ不足は本当に深刻で、貨物を送りたくても送れないという状況が続いています。
こんな状況なので冒頭でご紹介させてもらった、ジャパントラストの菅社長は「変えたい」と強く思っていらっしゃいます。
ジャパントラストの挑戦
ちょっとここで、ジャパントラストさんの「挑戦」を紹介させてください。
同社は日本→北米向けの貨物取扱量が世界で第6位のフォワーダーです。
グローバルフォワダーでもない社員25人くらいの名古屋の小さなフォワーダーが、世界6位とは本当に凄いことです。
現在、行われている彼らの挑戦は、なんと名古屋からアメリカのLA港まで、在来船を自社でチャーターすることです。
今回説明したように、現在 日本にはコンテナが集まりません。
これをフォワーダー1社で何とかしようというのも無理な話なんですが、ジャパントラストの社長は何か「挑戦する」ことで
日本の海運関係者たちの意識を変えようとされています。
そしてこの在来船のチャーターには3,000万円くらいの費用がかかり、同社のお客様の貨物を集めても2,000万円くらいにしかならず
残り約1,000万円が足りていない状況です。
ここでお知らせなんですが、同社はこの名古屋→LA港までの在来船チャーターの費用で、クラウドファンディングを実施されています。
「赤字になっても必ず運行する!」とのことですが、関係者様の支援を呼びかけています。
クラウドファンディングの詳細については概要欄にリンクを貼っておきます。
ちなみにですが、これは同社からの企業案件ではありません。
それどころか、私個人的にも支援をさせてもらっています^^
今後の日本の海運市場
もしこのまま日本の海運が変わらなければ、邦船や日本の市場はこれからどうなっていくのでしょうか?
もしかしたら外国の企業に買収され、日本に寄港する船が一気に減るなんてことも可能性としてはゼロではありません。
もし、そうなったら島国にある日本の企業は圧倒的に利便性を欠きますし、輸送を他国にコントロールされることにもなるのです。
私としては、今回ご説明させてもらったような日本の海運市場についても知っていましたし、現在コンテナが日本に集まっていないのも知っていました。
でも あまりにも大きな問題だし、自分で出来ることはないと思い傍観していました。
しかし、同社の挑戦を見て、日本のこれからの海運の為に、私自身が何か力になれないかと思い
今回の近代日本の海運の歴史と、課題を皆さんにお伝えしようと思った次第です。
まとめ
それでは今回の話をまとめてみましょう。
日本は島国で海運を使った貿易によって経済が成り立っています。
戦後にスエズブームで好況に移った海運市場ですが、この時に船を作り過ぎてしまい、ブーム終了時には反動で一気に不況が訪れます。
日本は好景気を迎える一方で、政治的な要因で円高に向かっていくことになり、生き残りをかけて買収や合併を繰り返し
日本の船会社は日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社だけが残りました。
そしてコンテナ事業はこの3社で合併されONEと2017年になりました。
海運市場は不況ですが、貨物の荷動きはグローバル化が進む中で、右肩あがりに増えていきます。
世界の船会社は海上輸送を合理化するために、船を巨大化させていくのですが、巨大化した船のスペースは、需要より供給が圧倒的に多くなってしまい
船会社同士で競争が激化していきました。
去年までは低価格運賃が続いていて、その中でも日本の海運市場は世界一安いと言われることもありました。
そして現在ではコロナウィルスが起因して発生したコンテナ不足となり、海上運賃は高騰したものの、
日本にコンテナが集まらないという問題が発生しています。
この問題に対して何か変えなければいけないと、ジャパントラストという名古屋の小さなフォワーダーが挑戦をしています。
私たち個人では出来ることは少ないかもしれませんが、私たち海運関係者の多くが歴史や現状を知り、
少しでも意識を変えることが出来れば、日本の海運がより良い未来に向かうかもしれません。
今回のお話がそのきっかけになれば嬉しいです。
今回のお話は以上になります。どうもありがとうございました!
・Twitter で DM を送る
https://twitter.com/iino_saan
・LinkedIn でメッセージを送る
https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/
お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。