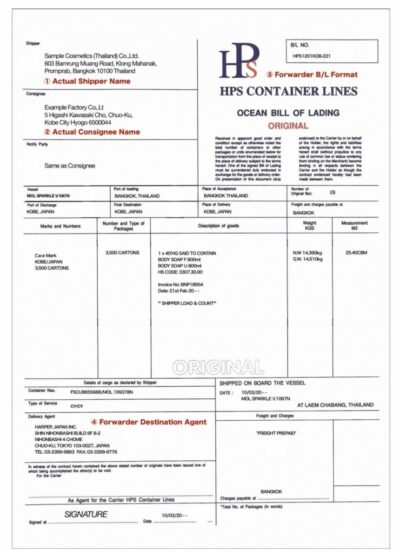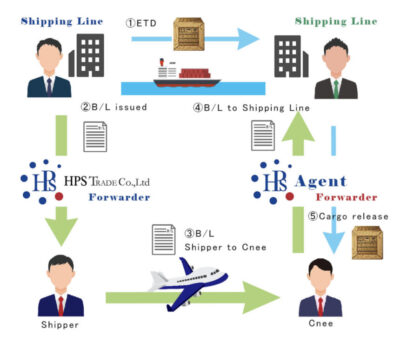2020.09.27
【タイ・バンコク】現在の日本食市場を解説!一般タイ人、富裕層などに向けた日本食マーケットを獲得する為に必要なこと。
タイに食品を輸入したいというお問い合わせや、輸入手続き依頼をお陰様で沢山頂いております。経済成長を続けるタイのバンコクでは食の選択肢がとても豊富で、日本食への需要も更に高まっています。 昨今ではバンコクの日本食のマーケットは飽和状態と言われています。確かに飲食店は厳しい競争にさらされていると思いますが、セグメントを分けて様々な日本食が流通しているのが事実です。 タイでの日本食のターゲットセグメントは単純に分けて3つあります。 ・一般のタイ人向け ・タイ在住の日本人向け ・タイ人の富裕層向け それぞれのセグメントのマーケットを筆者の視点から解説していきます。 一般タイ人への日本食 ここ数年で本当に多くのタイ系の日本食レストランが増えてきています。 特にビュッフェ形式(食べ放題)が人気で、内容にもよりますがTHB400〜THB800/人くらいの金額で日本食を楽しんでいるタイ人たちは多い印象です。 ハル ジャパニーズ・ビュッフェより ローカルで大人気のSiam Takashimaya 他にもSiam Takashimayaにある中島水産の低価格寿司が大人気です。 THB10〜20/個(35円〜70円)で色んな種類のお寿司を選ぶことが出来ます。 タイ人に人気のネタはサーモンで、寿司やお造りではとにかくサーモンが沢山販売されており、大量に輸入されているのか価格帯もそれほど高くありません。 豊富な種類の日本食 現在では多くの日本食屋さんがタイのマーケットに進出してきており、昼食・夕食時には多くのタイ人で賑わっています。 寿司、定食、焼肉、たこ焼き、居酒屋、うなぎ、焼き鳥、蕎麦、牛丼、カレー、とんかつ、天ぷら、鉄板焼き、などなど。タイで食べられない日本食はほとんどないと思うくらい。 価格帯はランチであれば店にもよりますがTHB150〜THB350/食ほどで食べられ、オフィスに勤めているようなタイ人をよく見ます。 しかし、これは屋台のタイ飯(THB40/食)に比べると3倍以上の価格。確実にタイ人の所得が上がり、物価も上がり、食に対しての好みも変わってきたという印象です。 日系のスーパーは日本食だらけ バンコクにで有名の日系スーパーは「フジスーパー」と「高島屋」です。加工食品のラックをみると分かるように日本から輸入品が沢山そろえられています。 バンコクに住んでいる限り日本食に困ることはほとんどないので海外では人気の赴任先なんです。 ラーメンや味噌なども豊富な種類が取り揃えられております。 ザ・日本をイメージさせる居酒屋が人気 タイ人で多く賑わっているのが大衆居酒屋の「剣心」と「恵美須商店」。雰囲気は外国人が持つ日本のイメージを表現しているのでとても人気があります。 価格帯もそれほど高くはなくオフィス系のタイ人がお酒とつまみを楽しんでいる感じです。 Makro - マクロでボリュームディスカウント アメリカのウォルマートのようなディスカウントストアがタイにもあります。ラックに高くまで積み上げられた食材や日用品。 この大型のショップでは世界各国から食品が輸入されており、その中に日本食もあります。 野菜・肉・魚・加工品などすべてが大量に仕入れられているので安く、筆者も毎週末マクロに買い物にきています。 タイの屋台の人や個人商店を経営している人もここから買っていると分かるくらい、業者のような人たちがいっぱいきています。 日本食レストランが広がる地域の変化 バンコクの日本人街はプロンポンやトンロー地域が有名ですし、今でもこの地域には多くの日本食レストランがあります。 しかし、最近になっての注目すべきはBTSを東に向かってオンヌットやプラカノン地域。この地域は家賃がプロンポンなどに比べるとお手頃で多くの日本人が住み始めています。 バンコクに住む日本人に対してのマーケットが広がっている感覚はありませんが、より日本食のセグメントが細かく分かれたという印象です。 以前だと日本食という一括りで表現できたものが、今では新潟料理、沖縄料理、熊本料理、北海道、神戸トンテキなどなど。日本食の選択肢がより広がっているという印象です。 タイ人富裕層への日本食 筆者の周りにも少しですがタイ人富裕層がいるのですが、とんでもなくお金持ちです。 そんなお金持ちの彼らも高級な和食に舌鼓をうっているのでしょうか、実際に非常に高級な和食レストラン、寿司レストランは存在します。 他にもシャインマスカットやイチゴ、桃、メロンなど高級なフルーツもSiam Takashimayaで目にします。 日本人の筆者ですら高いと思うほどの価格帯で、タイ人の富裕層に向けた販売戦略をしているのでしょう。 まとめ バンコクの日本食のマーケットは飽和しているというより、更にセグメント化されたターゲットに合ったものを提供するという形になってきています。 単に日本食だから売れるというマーケットではなく ・誰に対して ・どの価格帯で ・ライバルと比較してどのような強みがあるのか を明確なメッセージとして表現できる事がこれからのバンコクの日本食市場を獲得していく分かれ目なのかなと思います。 弊社では食品のFDA登録、輸入通関手続きをしております。もしタイに展開したい食品がありましたらお問い合わせください。