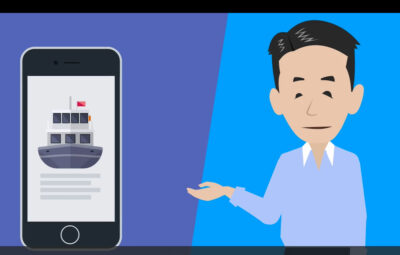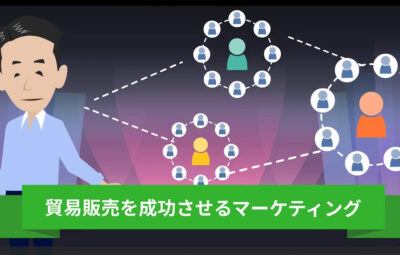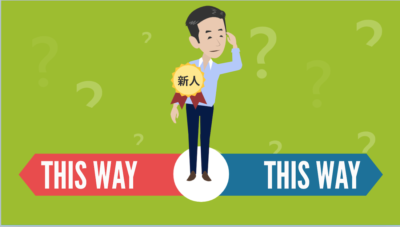2021.07.19
保税地域について
保税地域について動画で解説 どうもこんにちは。飯野です。 今回は保税地域というテーマでお話をしていきたいと思います。 以前の動画でも説明しましたが、貿易や国際物流には保税というものがあります。保税とは国内にありながらも、外国の貨物の扱いとなっている状態のことです。 詳しくは「保税の基礎」という動画で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。 この保税状態になった貨物を保管出来る場所は決まっていて、保税地域と呼ばれます。今回は保税地域の目的と機能を、詳しく見ていくことにします。 それではいってみましょう! 5つの保税地域 まず保税地域には、機能と目的によって次の5つの種類があります。 ・ 指定保税地域 ・ 保税蔵置場 ・ 保税工場 ・ 保税展示場 ・ 総合保税地域 今回説明している内容は日本の関税法に基づいたもので、他国の場合は名称や制度が異なりますのでご注意ください。 一つずつ見ていきましょう。 指定保税地域 まずは指定保税地域です。指定保税地域は国や地方公共団体などが所有し管理する、土地および建物などの 公共施設において、日本では財務大臣が指定した場所です。 この保税地域が国際物流で必ず利用される、コンテナヤードのことで、船から積み下ろした外国貨物を一時保管することが出来ます。また税関手続の簡素化、迅速化のために、各地の税関の近くに設置されています。 保税蔵置場 次に保税蔵置場です。保税蔵置場とはフォワーダーなどの自社の倉庫や貨物施設で、税関庁の許可を受けた施設です。いわゆる保税倉庫や上屋等がこれにあたります。 主に貨物の搬入、積み下ろし、保管を目的としています。輸入の場合、保管をしている期間は関税はかかりません。この場所で貨物を仕分けをしたり、ラベル貼りや簡単な作業をすることも出来ます。 保税工場 保税工場は、外国貨物の加工・製造ができる保税地域です。主に加工貿易をするために使用されます。輸入した原材料には税金はかからず、保税工場で加工を加えて再輸出をする事が出来ます。 魚介類の缶詰、菓子、鋼材、電線、船舶、自動車、精密機械など、様々な分野の製品が保税工場で生産をされています。 私が活動しているタイにおいては、FreeZoneと呼ばれる保税地域内に工場があります。国によってはこのように保税工場というものはなく、FreeZone内の工場として存在していると思います。 保税展示場 保税展示場は、外国貨物を展示する会場とされています。 外国貨物を関税を課さずに展示できる場所で、国際的な博覧会や商品の展示場として利用され、簡易的な通関手続で貨物を展示保管する事が出来ます。 もし この保税展示場を使用しない国際展示会であれば、再輸出免税制度やATAカルネを使用して免税手続きを取らなければいけません。 総合保税地域 総合保税地域は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場の3つの保税地域の総合的な機能を持っている保税地域とされています。 日本では中部国際空港や横浜国際流通センターなどがあります。 まとめ 今回は保税地域について説明をしました。貿易の初心者の方は、まず大まかに保税地域にはそれぞれ目的と機能があると理解して頂ければ大丈夫です。 次回は貿易において、なぜ保税が重要なのか?についてご説明をします。今回説明した保税地域の内容も関係しています。チャンネル登録がまだの方は、ぜひこの動画の終了時によろしくお願いします。 今回は以上です!ありがとうございました! ・Twitter で DM を送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedIn でメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/ お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。