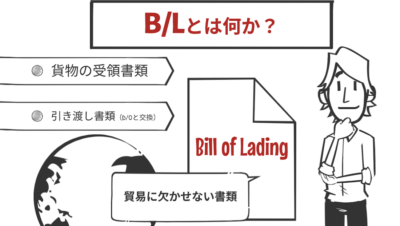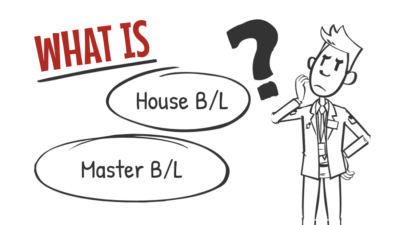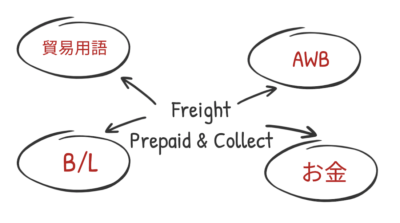2022.03.15
コンテナによる海上輸送のMaster B/Lが出来るまでの流れ
この記事を動画で見る どうもこんにちは、飯野です。 今回はコンテナによる海上輸送での、Master B/Lが出来るまでの一般的な流れについてご説明したいと思います。 Master B/Lとは Master B/Lとは船会社が海上輸送における貨物を受領し、目的地まで貨物を輸送することを証明する船荷証券です。 また、Master B/Lは複合輸送や三国間などの場合において、フォワーダーやNVOCCが荷主に代わってShipperになるときに、船会社が発行する有価証券でもあります。 ちなみに、フォワーダーやNVOCCが発行する船荷証券はHouse B/Lと呼びます。 Master B/Lを発行する為には、本船に積まれる貨物の情報や、発行通数などを船会社へ連絡・指示が必要になります。 それでは、Master B/Lを作成・発行する為の必要な情報の流れを説明していきましょう。 Master B/L発行必要書類 Master B/Lが発行されるまでには、いくつかの書類が必要となります。 主となる書類は船積依頼書(SHIPPING INSTRUCTION :通称 S/I)と、B/L INSTRUCTION があります。B/L INSTRUCTIONは、DOCK RECIEPT(通称ドックレ:D/R)などとも呼ばれています。 B/Lに必要な情報は、次の順番で船会社へ伝えられます。 ①S/I ↓ ②B/L INSTRUCTION ↓ ③Master B/L まずMaster B/Lに必要な情報の大元はS/Iです。そして、S/Iの情報がB/L INSTRUCTIONに反映されます。最後にB/L INSTRUCTIONの情報を基にMaster B/Lが作成されます。 では、S/I、B/L INSTRUTION、Master B/Lはどのように作成されるのでしょう? それぞれについて、ご説明します。 S/Iについて まず、S/Iは荷主によって、フォワーダーやNVOCC宛てに作成されます。 S/Iは、いつ・どの船で・どんな貨物を・どこからどこへ運ぶのか、どのようなB/Lを発行するのかを、フォワーダーへ指示・連絡する書類です。 S/Iの内容 では、ここからS/Iにどのような情報が記載されているか具体的に見ていきましょう。 ・荷主 (SHIPPER) ・受荷主 (CONSIGNEE) ・NOTIFY PARTY ・積載予定本船名 (VESSEL NAME) ・荷渡地 (PLACE OF RECEIPT) ・積地港 (PORT OF LOADING) ・CUT日 (CUT) ・本船出港予定日 (ETD) ・揚出港 (PORT OF DISCHARGE) ・最終仕向地 (PLACE OF DELIVERY) ・商品名 (COMMODITY) ・数量 (QUANTITY) ・重量 (NET WEIGHT) ・荷印 (SHIPPING MARK) ・運賃支払 (FREIGHT PREPAID or FREIGHT COLLECT) ・B/L発行通数 ・B/L発行地 などです。 S/Iのフォームは特に規定はなく、その会社独自のフォーマットを使用している場合が多いです。 荷主は売買契約の元、貨物を積む本船が決まり次第、S/Iを作成し、フォワーダーへ送ります。 尚、売買契約の決済条件がL/Cの場合、必ずL/CにどのようなB/Lを作成するか指示があります。 L/C決済の場合 L/C決済の場合、荷主はL/Cのリクエスト通りの書類を銀行に提出しなければなりません。 B/Lは有価証券、つまり貨物と同じ価値がある書類なのでL/C決済の場合には、L/Cの指示に沿ってS/Iと一緒にL/Cの情報もフォワーダーへ送ります。 B/L Instructionについて B/L INSTRUCTIONは、船会社にB/Lを発行してもらうための書類で、一般的にフォワーダーから船会社へ提出されます。 B/L INSTRUCTIONにはS/IやL/CのB/L作成に必要な情報にプラスして、貨物の総重量、総容積、数量が追記されます。 貨物の総重量、総容積、数量の情報は、VANNING REPORTと呼ばれる書類から確認することができます。 VANNING REPORTについて 尚、VANNING REPORTには、コンテナ1本あたりに積まれた貨物の情報が記載されており、主にこれらの項目があります。 ・貨物の重量(GROSS WEIGHT) ・貨物の容積(MEASUREMENT) ・貨物の数量 (QUANTITY) ・積載形状 (BAG, PALLETS, CARTONなど) ・CONTAINER NUMBER ・SEAL NUMBER B/L Instructionの送信 フォワーダーは荷主から入手したS/IやL/Cをもとに、船会社が指定するB/L INSTRUCTIONのフォームやフォワーダー独自のフォームを使用して、船会社へメールやFAXでB/L INSTRUCTIONを送信します。 また近年では、NACCSというシステムの船積確認事項登録(Access Control List 略:ACL)にて、B/L作成に必要な情報を船会社へ送信する方法が主流となっています。 このようにS/I、B/L INSTRUCTIONを介して、荷主からフォワーダーへ、フォワーダーから船会社へとB/L作成に必要な情報が伝えられて行きます。 Master B/L作成の流れ それでは次に、船会社のMaster B/Lの作成の流れをご紹介します。 お伝えした通り、近年ACLを介して船会社へB/L作成に必要な情報が送信されています。船会社は、送られてきたACLの情報を独自のシステムに取り込み、B/Lを作成しています。 もし、船会社とフォワーダーがACLで繋がっていない場合、船会社はB/Lに記載する情報を独自のシステムに手入力する場合もあります。 出来上がったMaster B/Lは、本船が出港した後に発行されB/Lの発行状況をホームページで確認できる船会社もあります。 お伝えした通り、Master B/Lが出来上がるまでに、S/IやB/L INSTRUCTIONといった書類、またはACLといったシステムを介して、B/L作成に必要な情報が各関係者へ伝えられていきます。 そのため、B/L作成に必要な情報がいずれかの段階で間違ってしまうことは珍しくありません。 間違った情報でMaster B/Lが発行されると、後にマニフェスト、通関、商品決済などに支障をきたしてしまいます。 そのため、各段階で作成される書類の内容を確認することは、とても重要です。 B/L Draftの入手 また、Master B/Lを発行する前に、B/LのDRAFTを入手して内容を確認しましょう。B/LのDRAFTとは、Master B/Lの下書きの段階の書類です。 船会社に依頼すればB/L DRAFTを送付してくれますので、Master B/Lを発行する前に内容を確認することができます。 もし、DRAFTの段階や、Master B/Lが発行された後に訂正が必要となった場合、再発行することは可能です。 B/Lの訂正 CUT日以降にB/L DRAFTの訂正を依頼する場合、船会社によっては訂正料が発生し、L/Gの提出が必要になる場合があります。 L/Gとは、その訂正が船会社の責任ではないことを保証する書類のことです。 正式依頼する前に船会社へ訂正料とL/Gの有無を確認しておきましょう。 尚、CUT日前の訂正であれば、訂正したACLまたはB/L INSTRUCTIONを船会社へ連絡すればよいので、訂正料とL/Gの提出は不要です。 一方、Master B/L発行後の内容訂正の場合は、訂正料が発生します。同時に、発行された全通数のMaster B/Lを船会社へ返却しなければなりません。 このように訂正するための追加料金の支払いや再発行にかかる時間を避けるためにも、各段階での書類の内容の確認をしっかり行うことが重要です。 まとめ Master B/Lが完成するまでには、色々な書類の情報が統合されています。そして、B/L作成に必要な情報は伝言ゲームのように各関係者へ伝えられていきます。 書類を作成する際には、その書類を使って次に作業をする人へ情報が正確に伝わるように書類作成を心掛けると良いのではないかと思います。 今回の内容はいかがだったでしょうか?為になったという方は、チャンネル登録、フォロー、SNSでのシェアを何卒よろしくお願いします! ではまた次の動画でお会いしましょう!ありがとうございました! ・Twitter で DM を送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedIn でメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/ お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。