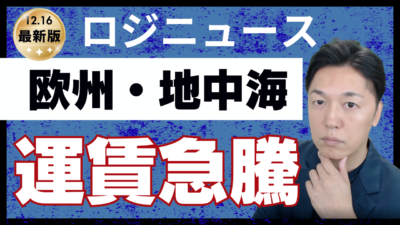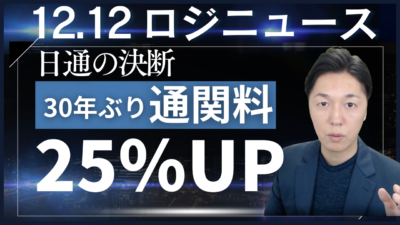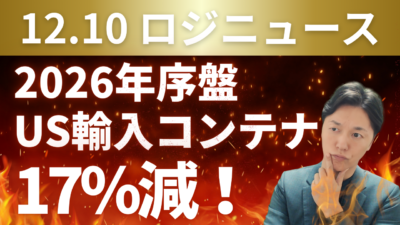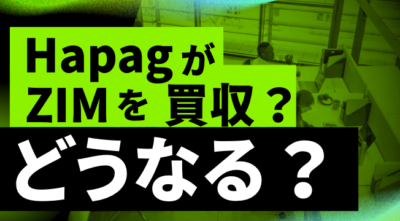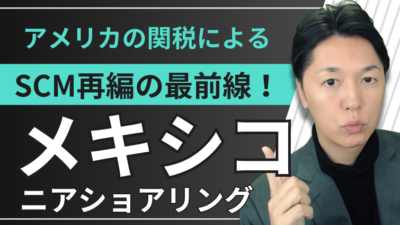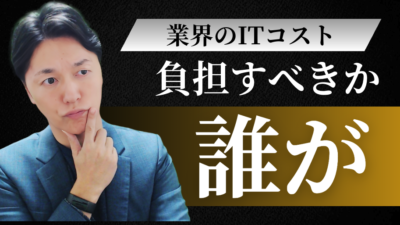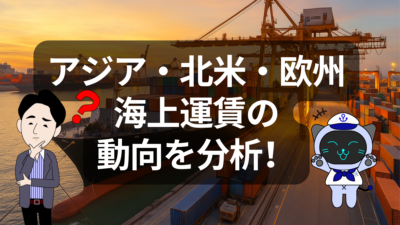2025.12.17
FP1改変の衝撃と、日本の港が突きつけられた4つの課題
本日のテーマは、ONEが運航する基幹サービスであるFP1の改変についてです。 今回の発表を一言でまとめると、日本発欧州向け直行便の事実上の終了と、釜山トランシップへの完全移行という二つの大きな転換点に集約されます。 この動きは単なる航路改編ではなく、日本の港湾が置かれている現実を浮き彫りにする出来事だと言えるでしょう。 動画視聴はこちらから FP1とはどのような航路だったのか FP1は正式名称をFP1 Pendulum Serviceといい、欧州とアジア、さらに北米西岸を結ぶ超長距離のペンデュラム型航路として運航されてきました。 日本の荷主にとって、この航路は極めて利便性が高く、東京や神戸といった主要港に欧州向けの本船が直接寄港することで、積み替えなしで貨物をヨーロッパまで輸送できる点が大きな強みでした。 リードタイムが安定し、積み替え作業がないことで貨物ダメージのリスクも抑えられるため、日本輸出を支える大動脈のような存在だったのです。 FP1改変によって何が変わったのか しかし今回、ONEはこのペンデュラム配船を分断する決断を下しました。 新しいFP1は欧州とアジア間の往復に縮小され、その寄港地リストから日本の港が外れる形となりました。 これにより、日本発欧州向けの貨物は、原則として釜山港でのトランシップを前提とした輸送へと切り替わります。 日本各港からはフィーダー船で釜山港へ輸送され、そこで欧州向けの大型本船へ積み替えられる流れになります。 ONEが示す表向きの理由 ONEが公式に挙げている理由は、大きく二つあります。 スケジュール定時性の回復 地政学的リスクへの対応 従来の欧州・アジア・北米を結ぶ長大な航路では、どこか一か所で遅延が発生すると、その影響が地球の裏側まで波及する構造的な問題を抱えていました。 航路を分断することで、この遅延の連鎖を断ち切り、定時性を改善したいという狙いがあります。 また、紅海情勢の悪化により喜望峰回りが常態化し、航海日数と必要船腹が増える中で、効率の悪い寄港地を削減せざるを得なくなった点も無視できません。 日本の港が直面する四つの構造的課題 ただし、これだけで今回の決断を説明することはできません。 なぜ日本発着ではなく釜山経由なのか。 なぜ日本の船社であるONEが、日本を抜港する判断を下したのか。 その背景には、日本の港が抱える四つの構造的課題があります。 課題① 荷物量の低下 日本から欧州へ向かう輸出貨物の絶対量は、長期的に見て減少傾向が続いています。 生産拠点の海外移転が進み、かつてのようなボリュームを日本単独で確保することが難しくなっています。 2万TEU級の超大型船にとって、荷物が十分に集まらない港へ寄港するメリットは、年々小さくなっています。 課題② 港の分散 日本の港湾は、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸と広く分散しています。 一方、釜山港は国策として機能を集約し、効率的なスーパーハブとして整備されてきました。 巨大船が日本の複数港を回って貨物を集める運用は、現在の市況では各駅停車のような非効率な形になっています。 課題③ コストと使い勝手 釜山港は24時間稼働を前提とした運用体制を整え、トランシップコストも低く抑えられています。 日本の港も改善は進んでいるものの、グローバル競争の中では依然として差があります。 船社の立場から見れば、日本各港で集荷するよりも、釜山一か所に集めてもらう方が、コスト面でも運用面でも合理的なのです。 課題④ 地理的なロス 日本はアジア航路の最奥に位置しており、欧州側から見れば行き止まりに近い場所にあります。 中国や韓国で折り返せば短縮できる航海日数が、日本まで寄港することでさらに数日延びてしまいます。 特に喜望峰回りが続く現状では、この数日のロスが船社にとって看過できない負担となっています。 FP1改変は、日本の港湾競争力の低下を象徴する出来事だと言えるでしょう。 物流担当者が考えるべき次の一手 今回のFP1改変は、単なる不便さの問題ではありません。 リードタイムの延長や積み替えリスクを前提に、物流戦略そのものを見直す必要があります。 他社欧州サービスとの比較検討 航空便との併用によるリスク分散 海外在庫拠点の活用 2025年以降は、日本パッシングという現実を前提にしたドライで実務的なサプライチェーン再構築が求められます。 物流が変われば、ビジネスの形も変わります。 今回のニュースを、単なる制約ではなく、次の一手を考えるきっかけとして捉えていただければと思います。