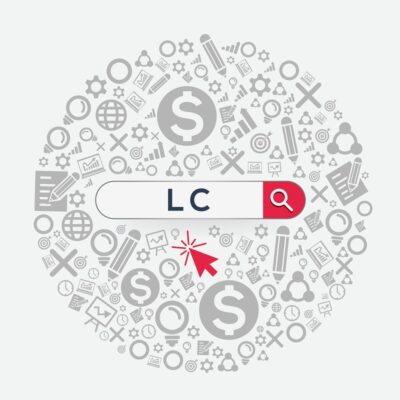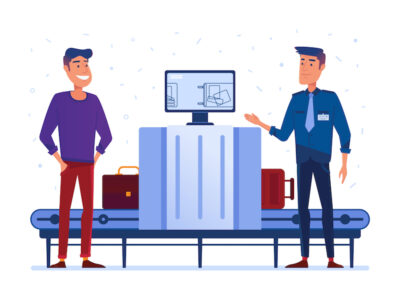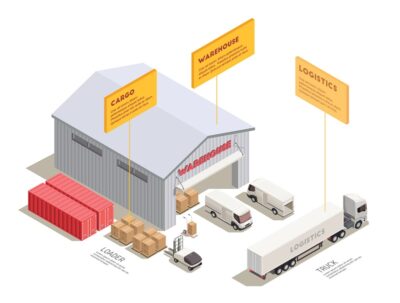
2020.10.19
保税輸送について解説!OLTやILT輸送のメリットや必要手続きなどをご説明します。
保税輸送を活用してコスト削減できることをご存知ですか? 保税輸送は、関税・消費税未納のまま外国貨物を保税地域間で運送する仕組みです。この制度を理解し活用することで、保管料の節約、税金支払いタイミングの調整、検品後の適正な通関申告など、輸出入ビジネスのコスト削減と効率化につながります。 保税輸送はなかなか聞き慣れない単語かもしれませんが、貿易をする上で知っておくと役にたつことがあります。 フォワーダーにとって保税輸送は毎日当たり前のように手配しているとても身近なものです。 保税輸送について知り、輸出入のビジネスでコスト削減につながる可能性もありますので、しっかり理解していきましょう。 この記事でわかること 保税輸送の定義と、外国貨物を保税地域間で運送する仕組み 保税輸送が必要な3つの場面(保税蔵置場・保税工場・保税展示場への輸送) 保税輸送を活用する3つのメリット(保管料節約・税金支払い調整・検品後通関) 保税輸送の手続きの流れと、包括保税輸送・特定保税運送者制度 保税輸送を活用したコスト削減をサポートします。まずは貨物の保管状況をお聞かせください。 保税輸送を相談する 保税輸送とは何か 保税輸送とは、指定保税地域や保税蔵置場などの相互間で、外国貨物のまま運送することです。 外国貨物というのは関税や消費税を払っていない状態で、国内にある貨物ではありますが保税地域に置かねばならず、税関の管理下にあります。 この外国貨物のままというのがポイントなのです。 ここで外国貨物というのをおさらいしておきます。 外国貨物は日本に到着したばかりで、輸入の申告の許可をうけていないもの、または輸出の申告をした後に税関の許可をもらったあとのもので船や飛行機に積みこんでいないものをさします。 外国貨物を決められた場所に置いていないと、税関の役割である税金の徴収が難しくなります。 そのため、保税輸送とは指定保税地域や保税蔵置所などの許可を受けた場所から外国貨物を動かす際には、前もって税関の承認をもらってから承認をもらった蔵置所等に動かす運送のことをいいます。 一般的には保税輸送はOLT(OVER LAND TRANSPORT)と呼ばれています。これは陸送による保税輸送をさしています。トラックやドレージによる輸送です。 ちなみに内航船などを使い船による保税輸送をILT(INTER CORST TRANSPORT)といいます。コンテナのフィーダーや原料の輸送などに使われます。 保税輸送が必要な場面 保税輸送は実務で輸出入の手配をしていると色々な場面で行われていると実感します。 以下にどのような場面で保税輸送が行われるか紹介していきます。 ①指定保税地域から保税蔵置場まで 輸入の場合 一般的には海上コンテナは、指定保税地域(ヤード)に下ろします。そこですぐさまに輸入通関を行い、通関許可になれば貨物は内国貨物として引き取れるので、保税輸送は行われません。 そして、すぐに通関できない事情などがある場合は、保税蔵置所などに保税輸送することになります。指定保税地域は保管期限が1ヶ月と短いため、それを超して蔵置することはできません。 保税蔵置所は長く蔵置することを目的にフォワーダーなどが税関から許可をうけて、保税蔵置所の許可をもらっているもののため、フォワーダー自身の倉庫や提携倉庫に保税輸送し保管や貨物の検品などを行った上で、輸入通関することができるのです。 LCL貨物の場合、指定保税地域(ターミナル)から保税蔵置場(CFS – Container Freight Station)に保税輸送されてから、それぞれの混載貨物として搬入されます。 輸出の場合 輸出の場合でも、LCLでは保税蔵置所(CFS)でバンニングなどをしてそこで輸出通関した場合は、指定保税地域(ターミナル)まで保税輸送します。 ②保税工場で加工、製造する 保税工場では外国から輸入した原料を税関に届け出た方法で保税工場で外国貨物のまま加工・製造ができます。 その行為をするために指定保税地域から保税工場まで保税輸送します。 ③保税展示場で展示・改装・仕訳をする 保税展示場では外国貨物のまま展示会でお客様に見せたり、注文をとったりすることができます。 指定保税地域や保税倉庫から保税展示場へ保税輸送し、そのまま外国へ積み戻すことができます。 保税輸送をする理由 ここでは保税輸送をする理由について、紹介していきます。 保税輸送はLCL貨物では必然的に保税輸送しなくてはなりませんが、そういう理由以外でも、うまく保税輸送を使うことによってメリットを生むことができるのです。 それについて説明していきましょう。 ①保管料の節約 船からおろされた貨物は指定保税地域(ヤード)に蔵置されますが、そこでフリータイム(無料保管期間)が過ぎた後の保管料(デマレージ)は高額です。 船の航路、コンテナの大きさや種類によって金額が違いますが、一定のフリータイムを過ぎると一日あたりどんどん金額が加算されていきます。 すぐに通関できないもの、引き取りできないものは保税蔵置所へ保税運送した方が保管料がかからずに済むことが多いです。 もちろん、保税蔵置所でも保管料はかかります。 1ヶ月以内に引き取りできるのであれば 指定保税地域で1ヶ月以内の範囲で保管しデマレージを支払った方がいいのか それとも保税蔵置所に保税運送し保管料と保税蔵置所での入出庫作業料とを比べて どちらがお得か検討したほうがいいでしょう。 ②関税、消費税などの税金の支払うタイミングを図ることができる 例えば品物を海外で安く大量に仕入れたとします。販売先が決まるまで保税蔵置所で保管して、売れた時点で輸入通関し税金を支払えば資金繰りがよくなります。 このように指定保税地域では1ヶ月しか置けない物を保税蔵置所に保税運送すれば保管期限が2年となるため、販売のタイミングで税金の支払いを行うことが可能になるのです。 ③品物を確認してから輸入通関できる 輸入申告する前に保税輸送をして保税蔵置所で点検・仕分け等の検品を行うと実際の貨物にあわせた申告ができます。 例えばワインを輸入するとします。 一部の商品にラベル不良やワインボトルの割れがあり、輸入商品の価値がなくなったとき、税関の承認を受ければ関税や消費税未納の状態で品物の滅却処分ができます。 コンテナ単位で内容確認をせずに輸入通関してしまうと、なかなか後から関税や消費税を取り戻すことは難しいのです。 保税輸送を活用した保管料削減、税金支払い最適化、検品後の適正通関をサポートします。貴社の輸入状況に合わせた最適なプランをご提案します。 コスト削減プランを相談する 保税運送の手続き 外国貨物を運送する際には、税関に前もって承認を得る必要があります。 保税運送の流れ 運送手段や運送先、記号、番号、品目、数量、価格等を記載した「外国貨物運送申告書」を作成し、税関に提出し承認を得ます。 必要があれば税関職員の検査があります。 関税額に相当する担保の提供を求められることがあります。 貨物の運送手段や距離等を踏まえて、相当と認められる運送期間を指定されます。 運送の承認を受けたものは、運送目録を蔵置場に提出した上でその確認を受けます。 運送目録を到着地の蔵置場に提出し、到着確認を受けます。 到着の確認を受けた日から1月以内に、「外国貨物運送申告書」を到着地の税関へ提出しなければなりません。 発送地、到着地の税関が同じ場合は簡易審査となります。申告価格等も必要なく、検査や担保の提供は求められません。 その他の保税輸送の制度 保税輸送は個別に一件ずつ手配するものだけではなく、包括保税輸送という制度があり1年以内期間を指定してまとめて申請することもできます。 船社のフィーダーやインランドデポへの定期的なコンテナ輸送に使用されます。 また、最近の認定事業者制度により保税輸送も特定保税運送者では保税輸送の承認をしなくても保税輸送が可能です。 まとめ この記事で押さえておきたいところ 保税輸送は外国貨物のまま保税地域間を運送。税関の事前承認が必要 保税輸送の3つのメリット:高額なデマレージ回避、税金支払いタイミング調整(最長2年)、検品後の適正通関 保税蔵置所は保管期限2年で、販売タイミングに合わせた資金繰り改善が可能 包括保税輸送や特定保税運送者制度で手続きを簡素化できる 保税輸送について、ご理解頂けましたでしょうか。 保税運送は外国貨物を蔵置している保税地域からその他の保税地域へ運送することにより、保管期間を延ばしたり、税金の支払いのタイミングを変えたりすることができます。 保税輸送を戦略的に活用することで、デマレージの高額請求を回避し、販売タイミングに合わせた資金繰りの改善、検品による不良品の適正処理など、輸入ビジネスの効率化とコスト削減を実現できます。 保税輸送は貿易をしている上で、理解しているとメリットを受けられることがあるので、この記事をしっかり読んでおきましょう。 保税輸送を活用したコスト削減をご検討の方へ。貴社の貨物の保管状況と資金繰りに合わせた最適なプランをご提案します。まずは現状をお聞かせください。 保税輸送を相談する