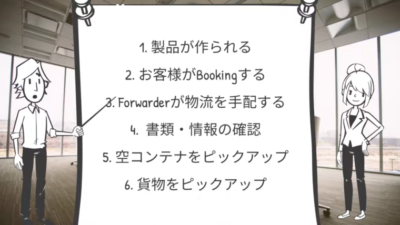2020.07.13
一般原産地証明の取得方法について!原産地証明を商工会議所で入手する方法について詳しく解説しました。
貨物を外国に輸送する時、貿易では原産地証明書を取得する場合があります。そして輸出で取得する原産地証明書は大きく分けて「一般原産地証明書」と、EPA経済連携協定に基づく「特定原産地証明書」の2種類があります。 どちらも「原産地証明書」という名称が含まれていますので不慣れな方は混同しがちだと思いますが取得目的も効果も大きく違います。 一般原産地証明 対象国:全世界 目的:輸入国側の法律や規則で必要。貿易取引の契約書や荷為替信用状(L/C)を運用 申請方法:窓口による書類申請 特定原産地証明 対象国:日本と経済連携協定を締結している国と地域 目的:EPA経済連携協定に基づき関税の優遇を受ける 申請方法:インターネットでの電子申請 どちらの原産地証明書を取得しようとしているかで、企業登録方法や申請手続もかなり変わってきますので、初めて取得をしようとするときにはご自分がどちらの証明書を求められているかをしっかりと確認してください。 今回は一般原産地証明書の取得方法について解説したいと思います。 特定原産地証明の取得方法は以下のリンク先の別記事にて解説していますが、それぞれに違いがありますので混同されないようにご注意下さい。 [keni-linkcard url="http://forwarder-university.com/epa-co/?lang=ja" target="_blank"] 原産地証明書とは? まず原産地証明書とは何かを簡単にご説明します。原産地証明書とはその名の通り、取引の対象となっている物品が特定の国又は地域で生産又は加工をされたことを証明する書類のことです。 貿易では基本的に関税を低くするために取得されることが多いです。英語では「Certificate of Origin」と表記されます。英文では「Cert」や「C/O」と略して呼ばれることもあります。 原産地証明書は輸出者が手配します。輸入の場合であれば輸出者から原本を入手するだけで基本的にはOKですので、取得方法は主に輸出者に関係する作業となります。 原産地証明書の全体像についてはこちらに記載をしました。 [keni-linkcard url="http://forwarder-university.com/certificate-of-origin/?lang=ja" target="_blank"] 一般原産地証明 さて以下に一般原産地証明書の取得方法について詳しく説明をしてきます。 一般原産地証明が必要とされるケース ・輸入国側の法律や規則で必要とされている場合 ・貿易取引の契約書やL/C(Letter of Credit)を使用するのに要求される場合 商工会の窓口のみで入手可能 一般原産地証明書は各地の商工会議所で窓口での書面申請により発給を受けることができます。郵送やメールで対応してくれる商工会議所は今のところ聞いたことがありません。 原産地証明書が必要とされる取引を開始する前に忘れずに商工会議所への登録を済ませて下さい。 さらに原産地証明書は原本でないと効果を発揮しません。 なので事前に原産地証明書用紙も商工会議所で購入しておきます。地域によって価格に違いはありますが窓口で100枚綴り500円程度で販売されています。 一般原産地証明の取得手続き さて船積が確定しましたら原産地証明書の発給手続きを始めます。各商工会議所のHPに印刷用のフォームがありますのでそちらに入力し、先ほど説明しました証明書用紙に印刷すると良いでしょう。 サインを除いてすべての記載事項を黒字または青字で英文で記載します。 記載ミスに注意 詳しい記載内容はここでは省略いたしますが、一字一句、決して間違いの内容に記載して下さい。窓口で申請する際にはかなり細かくチェックされます。 少しの間違いもないか何度も確認をしてから印刷をするようにしましょう。 サインも正確に 無事に記載事項が証明書用紙に印刷できましたら、サインを入れます。このサインは先に述べました貿易証明登録の際に商工会議所へ提出したサインでなければなりません。発給の際には登録のサインと相違がないかをしっかりとチェックされています。 少し自体が崩れているというだけで発給が不可となるケースもあります。なので他人の筆跡を真似てサインをしてもまず間違いなく見破られますので必ずサイン登録した本人がサインします。あらかじめ複数人のサインを登録しておくと安心ですね。 本人のサインであっても、登録の際と同じようなサインが書けるように十分注意してください。 商工会議所にて申請する 書類が準備できましたら商工会議所へ持参し発給申請をします。申請の際に一部は商工会議所側での控えとなりますので、ご自分の必要な部数 プラス 一部を持参するようにしてください。 窓口は平日の日中しか開いていません。夜間、土日は対応してもらえません。また、年末年始など混み合うときは午前で申請締め切りなどイレギュラーな対応となることもあります。 持参される際には窓口の空いている時間や申請の締め切り時間をあらかじめ確認しておく必要があります。 一般原産地証明所発行の手数料 申請の際にも手数料がかかります。こちらは1件あたり1,000円程度となります。券売機で必要な手数料分のクーポン券を購入して、それを申請書類と一緒に提出するスタイルです。 喫茶店のコーヒーチケットのように、10枚の値段で11枚綴りなどお得な冊子式クーポン券も各地で発売されていますので、度々原産地証明書を申請される方は購入されても良いでしょう。 無事に審査が通りましたら発給印やサインなどの入った原本が返却されます。後は現地へ送るなどすれば輸出側の手配は終了となります。 フォワーダーに依頼 申請手順としてはこんな感じでそれほど難しいものではありませんが、商工会議所へ出向いたりするのは少し手間に感じられますよね。お忙しい方は多少手数料が取られますがフォワーダーへ依頼するのも一つの手です。 商工会議所への申請はもちろん原産地証明書の作成から引き受けてくれるところも多いので料金がかかっても手間を減らしたい方はぜひフォワーダーに相談してみて下さい。 フォワーダーに依頼する際の注意点 フォワーダーに依頼する際の注意点ですが、フォワーダーが作成したとしてもサインは必ず貿易登録通りでなければなりません。 毎回、フォワーダーが作成したものを送ってもらってそれからサインしていては逆に手間ですので100枚綴りの証明書用紙を購入し、そちらに全てサインを入れてフォワーダーに預けておくという形で進めるとスムーズです。 これを受け入れていただけるかどうかもフォワーダー次第だと思いますので要相談です。 ちなみに、このやり方にOKが出てサインを入れる際ですが100枚一気にサインを入れると手が疲れてきてしまい、後半はサインが崩れてきて商工会議所からNGが出るレベルのサインになってしまう方も時々いらっしゃいます。 まとめ 一般原産地証明書の取得手順についてざっとお話ししましたがお分かり頂けたでしょうか。窓口でしか発行してもらえない書類ということで手間な側面はありますがまとめてサインをする、フォワーダーに依頼をするなどで対応が可能です。 是非ご参考にして下さい。