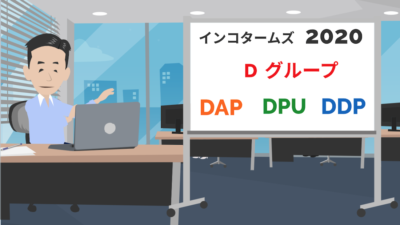2022.01.21
アライバルノーティスの役割と貨物引き取りの流れ
この記事を動画で見る どうもこんにちは、飯野です。 今回は貨物の輸入の際に登場する書類、アライバルノーティスについて解説したいと思います。この書類は貨物を引き取る際に必要なとても大事な書類です。 この動画では、アライバルノーティスの役割と、貨物を引き取るまでの流れを解説していきます。 アライバルノーティスとは アライバルノーティスとは、輸入国に貨物が到着する前に船会社から発行される「貨物到着案内」を指します。 英語ではArrival Noticeと記載し、「A/N」と略されることが多いです。 輸入者は、アライバルノーティスを受け取ると貨物を引き取る準備を進めることができます。基本的には、フォワーダーが輸入者に代わって引き取り作業を行います。 フォワーダーは少しでも早く輸入者に貨物を届けられるように、この引き取り作業を迅速かつミスがないように処理しなければなりません。 アライバルノーティスの内容をよく理解していないと、貨物を引き取る工程でトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。 アライバルノーティスの役割 アライバルノーティスの役割は主に次の3つです。 ・船社からの請求明細書 ・入港スケジュール・搬入先の通知 ・フリータイムの確認 フォワーダーは上記3点を確認し、引き取り準備にかかります。 それぞれ詳しく解説していきましょう。 船社からの請求明細書 まず請求明細書としての役割について解説します。 明細は海上運賃と共に、アライバルノーティスの下部に記載されていることが多いです。 主な費用項目を紹介します。 ・Ocean Freight(O/F) ・Terminal Handling Charge(THC) ・Delivery Order Fee(D/O fee) ・Documentation Fee(Doc Fee) ・Bunker Adjustment Factor(BAF) ・Currency Adjustment Factor(CAF) Ocean Freightとは、その名の通り海上運賃です。 輸入者側が海上費用を負担するインコタームズ(EXW/FAS/FCA/FOB)、あるいは慣例として輸入者が支払う場合に記載されます。 THCは、荷揚げや保税地域での作業を含んだコンテナの取り扱い料金です。貨物がLCLの場合は、さらにCFS Chargeが発生します。 D/O Feeは、輸入貨物を引き取る際に必要なD/Oを船会社から発行してもらうための手数料のことです。 Doc Feeは、船会社にB/Lなどの船積書類を発行してもらう費用です。 そのほかにも、BAFやCAFといった燃料や為替状況によって変動する割増料金などがあります。 こうした割増料金が発生する際は事前に船会社から通知される事が多いですが、連絡なく費用に含まれている場合は、念のため船会社へ確認するようにしましょう。 入港情報の通知 次に、入港情報の通知としての役割について説明します。 アライバルノーティスが手元に届いたということは、近日中に貨物船が港に到着するということです。引き取り作業を速やかに行うためにも、搬入先(CY/CFS)は要チェックです。 東京港や大阪港といった規模の大きい港だと保税地域が複数あるため、誤って違う搬入先を配送会社に伝えてしまう可能性があります。 搬入先に向かう配送業者に迷惑をかけるだけでなく、遠回りした分の配送料が加算されたり、最悪の場合、当日の間に引き取れないこともあります。 フリータイムの確認 最後に、フリータイムの確認について説明します。 フリータイムとは、輸入貨物を港の保税地域に無料で保管できる期間を指します。一般的にコンテナの無料の保管期間は1週間前後ですが、船会社ごとに期間は異なるので確認するようにしましょう。 この無料期間を過ぎてしまうと、デマレージ(超過保管料)が発生してしまいます。 アライバルノーティス発行からの流れ さて、ここからはアライバルノーティスが発行されてからの流れを説明します。 アライバルノーティスは、B/Lのノーティファイパーティ欄に記載された企業(買主又はforwarderなど)に通知されます。 通知先が輸入者のこともありますが、今回はフォワーダー宛として説明していきます。 フォワーダーから輸入者へスケジュール連絡 アライバルノーティスがフォワーダー宛にメールまたはFAXで送付されます。 入港スケジュールと搬入先を確認し、輸入者へお知らせします。急ぎの貨物の場合、輸入者は到着の連絡を待っているので速やかに連絡するようにしましょう。 船会社への支払い フォワーダーが請求内容を確認して、船会社へ支払います。 ここで注意すべきポイントは、「海上運賃」の記載の有無です。 まれに運賃前払い(Freight Prepaid)にも関わらず、費用項目に海上運賃が記載されていることがあります。そのときは船会社へ連絡をして訂正してもらうか、一旦支払い、次回振込時に相殺処理を行ったりします。 支払い方法 また、支払方法はアライバルノーティスに記載されています。多くが指定口座への振り込みですが、カード決済も最近では導入されています。 オリジナルB/Lの提出 オリジナルB/Lの場合は、B/L原本も船会社へ提出する必要があります。 オリジナルB/Lは有価証券の役割も持ち 取り扱いが難しいため、SEA WAYBILLを使用する場合もあります。 D/O発行 船会社は、支払いを確認するとD/Oを発行します。 D/OとはDelivery Orderの略で、船会社がCYオペレーター、または、CFSオペレーター宛てに発行した荷渡し指示書のことです。CYやCFSの保税地域で貨物を引き取る際に必要な書類です。 D/Oレスの確認 最近はほとんどの船会社がD/Oレスという形で、D/Oの書類発行をしていないため、支払いが完了すればリリースできることが多いです。 しかしD/Oレスだと勘違いをして、D/O原本が必要だった!というケースもあるので、しっかり確認するようにしましょう。 輸入許可、納品 あとは、税関から輸入許可が下りれば完了です。フォワーダーは、「D/O」を配送業者へ渡します。 そして、配送業者は保税地域へ貨物を引き取りに行き輸入者の指定する納品先へお届けします。 以上が、アライバルノーティスを使った貨物の引き取りの流れです。押さえるべき点を理解していれば、そこまで難しいことはありません。 まとめ 最後に、アライバルノーティスの役割3つと、注意すべき2つのポイントを確認して、今回の説明を終えたいと思います。 【役割】 ・船社からの請求明細書 ・入港スケジュール・搬入先の通知 ・フリータイムの確認 【注意すべきポイント】 ・海上運賃の支払い責任は誰なのか ・D/Oレスになっているのか これらが重要なポイントでした。 いかがだったでしょうか。 今回はアライバルノーティスの役割と、貨物のリリースの工程を紹介しました。 アライバルノーティスは、輸入地側の船会社が発行する重要な到着通知です。手元に届いたら、速やかに処理を行うように心がけましょう。 今回の動画がお役に立てましたら、チャンネル登録やいいねボタンを宜しくお願いします! ではまた次の動画でお会いしましょう!ありがとうございました! ・Twitter で DM を送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedIn でメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/ お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。