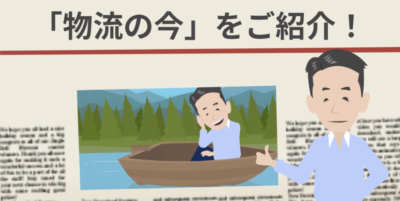この記事を動画で見る
どうもこんにちは飯野です。
今回は2021年8月の物流や海運に関するニュースをお届けします。「物流の今」を知りたい方に、役立つ情報を厳選しましたのでお楽しみ頂ければと思います。
それでは、いってみましょう。
中国・寧波港、感染者発生。一部コンテナターミナル封鎖により物流へ影響か
中国・寧波港で11日新型コロナウイルス感染者1名が確認され、同日より感染者が発生した寧波港梅山島コンテナターミナルは閉鎖になりました。
寧波港は中国港湾のコンテナ取扱量では第2位の規模を誇り、華東地区では上海港と並ぶコンテナ物流の重要拠点です。
そのため、今年5月末にコロナ感染者が発生した塩田港と同様の港湾混雑や物流の混乱が懸念されています。
17日現在寧波港で閉鎖されているコンテナターミナルは、梅山島だけで他の主要ターミナルは通常通り稼働しており、現時点では国際物流への影響は限定的ですが、長期化すると大きな問題につながるでしょう。
オーシャンネットワークエクスプレス(ONE)の13日発表した文書では、「梅山島コンテナターミナルの停止による衝撃は今のところ大きくない。ただ、梅山島に寄港予定だった一部船舶が他のターミナルへ寄港を変更するために、今後は影響がでてくるだろう」と見解を示しています。
上海空港、コロナ感染者発覚により貨物輸送便に混乱
中国・上海浦東空港の混乱が深刻化しています。8月21日に新型コロナウイルスの感染者が新たに確認され、21日の午前中から航空貨物の取り扱い機能が事実上停止していた模様です。
23日から上屋業務の一部が再開されましたが、貨物便の運休や受託の停止・制限が拡大しています。旅客便のベリーや運航中の貨物便のスペースも逼迫(ひっぱく)しており、航空運賃も上昇しています。
最悪、混乱は数週間続くとの観測もあり、例年9月からは欧米でのクリスマス商戦に向けた荷動きが活発になり、混乱が長期化すれば問題の影響は大きくなるでしょう。
北米西岸、再び沖待ち渋滞悪化
ロサンゼルスとロングビーチ両港には、ここ数日37隻のコンテナ船が停泊しており、2月以降で最も多い数となっています。
これはアメリカの年末商戦や在庫の補充のためもので、荷主がホリデーシーズンの輸入品を前倒ししていることが起因しています。アメリカ中西部の主要なハブでは、西海岸からシカゴへの輸送を制限するほど、コンテナが山積みになっています。
ターミナルでも記録的な量のコンテナがトラックや鉄道のキャパシティを圧迫しているため、コンテナが積み上がっています。
そのため内陸部に移動するまでのコンテナの保管期間がコロナ前では平均2~3日、現在では平均9~10日と状況は悪化しています。
ベトナム港湾混雑が悪化。カトライ港で大型貨物の引き受け制限
新型コロナウイルス感染が再拡大しているベトナムで7月下旬から主要都市でロックダウンが実施され、物流に影響を及ぼしています。
ベトナム港湾では昨年来の物流増加で混雑が続いていましたが、ロックダウンによる移動制限で労働者の確保が難しくなっています。
更に工場の稼働停止で輸入コンテナの引き取りがされず、コンテナが港に溜まり港湾の混雑が深刻化しています。
南部ホーチミンに近いカトライ港を運営するサイゴンニューポートは、大型貨物の引き取りを停止。輸入貨物の早期引き取りを依頼し、混雑解消を呼びかける通知をしました。
日系物流企業の現地駐在員は、「工場の操業停止が長引けば部材輸入も減速し、混雑が緩和する可能性はあるが基本的には輸出が堅調。空バンのピックアップを他のインランドデポにするなどカトライ集中を是正しない限り、荷役停止などもあり得る」と懸念を示しています。
DHL Express 12機の電気航空機を購入
DHLは8月3日、Eviation社から12機の電気航空機を購入し、すべての路線で運航することを発表しました。
声明の中で「クリーンなロジスティクスを実現するためには、あらゆる輸送手段の電気化がゼロエミッションという目標に貢献する。」と述べています。
電気航空機「Alice eCargo plane」の積載量は約1,800kg、航続距離は815km。飛行中の充電に必要な時間は30分以内とのことです。DHLは2023年までにCO2排出量を削減する取り組みに70億ユーロを投資し、2050年までにCO2排出量をゼロにすることを約束しています。
マースク、物流事業者2社買収し、さらなるは買収に乗り出す
世界最大手船会社マースクは約10億ドルに相当する買収を実施しました。
米国ソルトレイクシティを拠点とするVisible Supply Chain Management LLCと、オランダを拠点とするB2C Europeの2社の買収になります。
今回の買収は倉庫業、通関業、トラック輸送技術の分野での買収、投資に関わるもので、マースクの事業拡大が海上貨物から内陸物流へと拡大すること表しています。
マースクは世界的な海運市場の好況も影響し、堅調な収益を報告。主力事業であるマースクラインの輸送量は前年同期比で15%増加し、平均運賃は59%上昇しました。
好調な業績の中、更により大きな買収の可能性も示唆しています。
DSVパナルピナ、アジリティの事業買収完了。世界第3位に
国際物流大手DSVパナルピナは16日、中東物流大手アジリティの一般貨物部門グローバル・インテグレーテッド・ロジステイクス(GIL)の買収が完了したと発表しました。
これにより、DSVパナルピナの売上高は1,600億DKK(約2兆7700億円)となりました。
今回の事業買収により業界では、ドイツポストDHL、キューネ・アンド・ナーゲルに次いで世界第3位となります。
DSVパナルピナはフォワーディング事業の拡充や、中東、アジア太平洋地域で事業拡大を見込みます。アジリティが所有する倉庫約140万平方メートルも活用し、欧州、中東の陸送を強化するとのことです。
解説コーナー
それではニュースの解説のコーナーに参りましょう。
8月は物流の混乱につながるような問題が多かったなという印象です。特に中国ですね。中国の寧波港、上海空港での機能停止はサプライチェーンに大きな影響を実際に与えています。
寧波港は世界で第3位のコンテナ取扱量のある巨大港なんです。ここが混雑してしまうと、船は混雑を避けるために寧波港を抜港して上海などで積み込み・積み下ろしをします。
そうなると上海港が混雑する可能性もあり、上海港で本船スペースの確保が難しくなったりして、海上運賃の高騰につながる可能性もあります。
そして上海空港も同様に混乱し始めています。上屋で荷物をハンドリングするマンパワー不足になっていて、通常は2−3時間で終わっていた作業が6-10時間ほどかかるようになり、離職する人たちも増えてきているとのことです。
上屋での作業に時間がかかっているから、輸出では貨物が空の状態で飛ぶ旅客機があったり、輸入では貨物を積んだまま次の空港に向かう飛行機もあるみたいで、非常に混乱をしています。
航空運賃も実際に上がっていて北米向けで約USD1.5-3/kg, 欧州向けでUSD0.7-1.5/kgも上がったりしているそうです。今後どの様になるかが本当に注目です。
そしてアメリカの港の混雑が8月から再発生してきました。通常北米のクリスマス商戦への貨物需要は9月からなんですが、昨今のサプライチェーンの乱れで8月に前倒しになっています。
本当に北米向けのコンテナ輸送はスペース確保が難しくて、タイ初のロングビーチやニューヨーク向けでは弊社でも多くのお問い合わせを頂いております。
幸いスペースが取れるケースも多いのですが、海上運賃が高くて送るだけで赤字になるという荷主さんもいる模様です。
混雑や価格に落ち着きが見え始めるとしたら中国の国慶節が始まる10月以降でしょうか。
更にベトナムのロックダウンも物流に影響を与えています。先日、ベトナムのフォワーダーさんとオンラインで話をしたんですが、工場は稼働し始めているけど通常より生産量が落ちて仕事も減っているとのこと。
とにかくはワクチンが流通して1日でも早い回復を祈るばかりです。
現在、物流は混乱しているのですが大手企業各社は次々に国際的な環境テーマである脱炭素に向けての活動を始めています。その中でDHLの電気航空機には驚きました。
まさか電気で貨物機が飛ぶ時代が既に来ているなんて全く知らなかったので、こういうニュースにも注目をちゃんとしないといけないなと思いました。
この電気航空機の機体ですが未来的でカッコいいんですよね。若い人たちがより物流に興味を持ってもらえればいいなと思います。
そして最後に大手物流企業による買収です。これは先月もお伝えしましたが、昨今の船会社や大手フォワーダーは非常に儲かっています。
これを機に事業拡大のために物流業界でM&Aが日々行われている感じですが、今回は海運会社のマースクが内陸の物流を取りに行ったというのが注目でした。
またDSVパナルピナとアジリティの合併。大手企業同士の合併で更にスケールメリットを活かしてシェアの拡大を目指していくものと思われます。
コロナ以降の物流業界では船会社は限られたスペースを高く売って大きな利益を出し、大手フォワーダーはスケールメリットを活かして船社からのスペースを確保しています。逆に中小のフォワーダーだとスペースが取れない会社も実際にあったりします。
そういう意味で大手企業は得た利益で投資やM&Aを実施し、更に大きくなっていき、スペースが取れない中小フォワーダーは仕事が取れず生き残りが厳しくなるかもしれません。
まさに後期の戦国時代の様な感じでプレイヤーが限定されてきた印象です。
私自身も他人事ではなくしっかりと経営の舵取りをしなければいけないなと思っている今日この頃です。
今回の物流ニュースはいかがだったでしょうか。
今回参考にしたニュースのソースは概要欄にリンクを張っておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。
あと、最近はイーノさんの物流ラジオという企画でYouTubeとスタンドFMで音声配信をしています。
主に日々のニュースや物流に関する雑談を毎日更新していますので、もしよろしければそちらの登録やフォローもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っておきますね。
それでは、現場からは以上でーす!ありがとうございました。
・Twitter で DM を送る
https://twitter.com/iino_saan
・LinkedIn でメッセージを送る
https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/
お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。