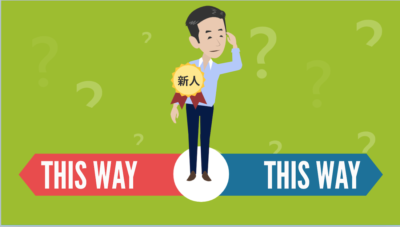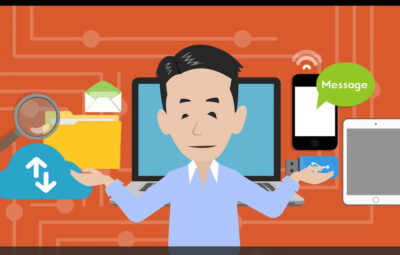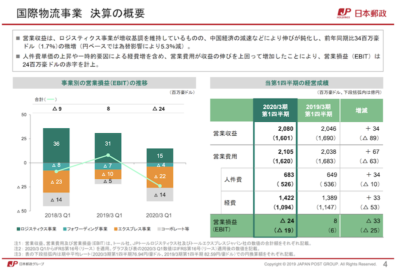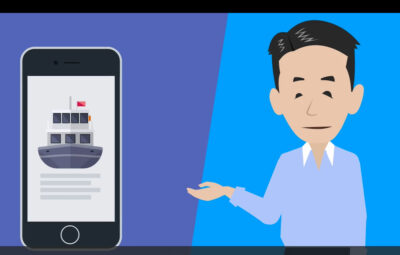
2021.06.07
2021年5月物流ニュース
2021年5月物流ニュースを動画で見る どうもこんにちは飯野です。 今回は2021年5月の物流ニュースをお届けします。前回に引き続き、最近の物流や海運に関するニュースをまとめてみました。「物流の今」が分かるように解説していきたいと思います。 それでは、いってみましょう。 コンテナ不足、長期化も。9月までか? 世界的な海上コンテナ不足に収束の兆しが見えていません。 昨年秋から悪化に拍車が掛かったコンテナ不足ですが、当初の今年2月まで、遅くとも5月までには落ち着くという予想が外れ、状況には変化がなく長引く気配が続いています。 海外主要港湾の混雑解消は目処がたたず、最近では9月ごろまで混乱が続くという見方が広がっているようです。 コンテナ船業界にとって重要な米国西岸ロサンゼルス(LA)、ロングビーチ(LB)では沖待ちが減少したものの、混雑の解消のために他の港に 多くのコンテナ船が向け地をシフトしておりカナダのバンクーバー港や北米東岸のサバンナ港でも沖待ちする状況になっています。 コンテナ不足はコロナ禍による巣ごもり需要で、荷動きが配給を上回ったことに加え、港湾やトラックの労働者不足が影響しています。 それによりコンテナ貨物の滞留を引き起こし、コンテナのターンタイム(返却されるまでの所要日数)が通常により長期化しているのが原因となっています。 米国のコンテナ船社関係者によると、「収束にはあと3~4ヶ月」「正常化には3~6ヶ月」との声があがっています。 北米西海岸 輸入コンテナ、2ヶ月連続100万TEU超え 次のニュースです。「北米西海岸 輸入コンテナ、2ヶ月連続100万TEU超え。コンテナ運賃上昇に歯止めかからず」 国際海運団体BIMCO(ボルチック国際海運協議会)によると、北米西岸港湾の輸入コンテナ取扱量は110万TEUで、2ヶ月連続100万TEUを突破。 過去10ヶ月では今年の2月を除き、9ヶ月で100万TEUを超えています。1月〜4月は前年同期から4割増で、5月以降も堅調が予測されます。 米政府は追加景気対策として3月に1人当たり1,400ドルの給付をしており、小売業の売り上げを押し上げ、それに比例してコンテナ輸入量も高水準となっています。 BIMCOの分析によると、小売りの販売が好調で在庫の補充も必要となるため、去年のサプライチェーンの混乱対策として通常より前倒しで輸入を行う可能性があり、5月以降の物流を押し上げるとのことです。 コンテナ運賃上昇に歯止めかからず コンテナ運賃に関しては高騰が止まりません。 5月14日付の上海発 北米東岸向けコンテナのスポット運賃は40フィートコンテナ当たり7,378ドルとなり、この1ヶ月あまりで2,000ドルも値上がりしてます。 北米西岸向けは4月末に5,000ドル超え。また北欧州・地中海向けも20フィートコンテナが5,000ドルを初めて突破するなど、最高値を更新しています。 IMO, 自動運航船のルール策定へ IMO(国際海事機関)は自動運航船の国際ルールを策定のために、SOLAS条約の改定する方針であることを発表しました。 自動運航船の国際ルールを決めるために、今後条約の改正や解釈を変更する必要があり、その中でも無線通信、航海の安全と海上保安の章に自動化システムの定義を取り入れることになるそうです。 また、船舶自動識別装置の互換装置として開発が進められている 衛星VDESについて、これもSOLAS条約の航海機器と扱われるように検討されることが決められました。 VDESは洋上における通信情報ネットワークで高い通信能力があり、将来的には画像の送受信ができ 船舶のより安全な運行に貢献することになりそうです。 新造船発注数、前年比43%増 造船マーケットも活気づいています。 ベッセルズ・バリューマーケット・リポートでは新規造船の発注が増え、2021年1~4月の新造発注隻数は352隻で前年同期比の43%増と伝えています。 また同期間の総発注金額は169億6,000万ドルで、前年同期の2.1倍と活況の数字を示しています。 コンテナ船輸送時間の大幅増により、景気回復の足かせに ここからは、アメリカからのニュースです。 今年に入ってから貨物船の荷役時間が大幅に増加しコンテナ船の遅延を引き起こし、輸送能力と在庫を圧迫しサプライチェーンの混乱を招いています。 デンマークのSea-Intelligence ApS社の分析によると、3月に世界の港に到着したコンテナ船のうち、時間通りに到着したのは約40%に過ぎず、平均で6日以上の遅れが発生しています。 過去2年間では70%以上の船が定刻に到着していました。 マースク社のVincent Clerc氏は、「上海からロサンゼルスまでの航海には通常14日かかるが、現在では33日かかっている。運行時間は同じだが、荷降ろしを待つ時間は2倍になっている。」と語っています。 脱炭素化、一部 懐疑的な意見も 米国が推進する脱炭素化船舶について、業界内で意見が分かれています。 バイデン政権は船舶のCO2排出量を大幅に削減することを求めていますが、非化石燃料を使うことにより輸出コストの上昇を恐れるアジアや南米の国から反発を受けることになりそうです。 今年4月、米国のジョン・ケリー特使は、IMO(国際海事機関)は2050年の温室効果ガス排出量をゼロにするというより厳しい目標を推進すべきだと述べましたが、日本や一部の北欧諸国のメンバーは米国の要求に加わることが予想されます。 一方でブラジル、アルゼンチン、アフリカ諸国などでは、目標を支持する条件として、補償を求める国もあるようです。 IMOの審議に詳しい関係者によると、中国は発展途上国とともに、新燃料への移行を容易にするため、新たな要件の例外を求めたり、資金援助や技術移転を求めたりする可能性が高いと予想しています。 2050年までに温室効果ガスゼロを達成できるかどうかについては、業界内でも懐疑的な意見が多く、脱炭素化船舶への取り組みはまだ初期段階と言えるようです。 解説コーナー はい、それでは今回ご紹介した、ニュースの解説のコーナーです。 昨年の10月から続いているコンテナ不足の解消見込みですが、やはり後ろ倒しになっていますね。3月末にエバーグリーンの船が約1週間、スエズ運河を封鎖した影響もありピンと張り詰めていたコンテナの流動性が崩れ落ちたのも影響していると思います。 それに伴い、アメリカ向けで本当にスペースが取れず、海上運賃の高騰も 現場で働いている私としても、凄く実感しています。私のYouTubeを見て頂いた荷主さんから、アメリカ向けのスペースを取って下さいという問い合わせは本当に多いです。 弊社でも出来る限りのことをしていますが、流石にお約束できるという状況ではありません。 またIMOがSOLAS条約を改定する方向で動いていますね。 SOLAS条約とは船舶の安全確保を目的とする国際条約で、最近の改訂だとコンテナの重量を規制するVGMがありました。今回の条約改定のきっかけはスエズ運河の座礁問題も影響しているのではないかと思います。 テクノロジーが発達し、船舶の自動運航も進んでおり、車の自動運転でも法律の整備が行われるのと同じように、船舶の自動運航システムのルール作りがこれからも重要になってくるでしょう。 造船マーケットも盛り上がっています。 発表されている船会社の決算結果を見れば分かるように、現在の海運マーケットは好況を迎えています。 それに伴い、造船や新しいコンテナの発注も増えているんですけども、これって別の動画でも解説した1956年のスエズブームの時と同じで、この後で高い確率で過剰供給になると思うんですよね。 そうなるとまた値下げ合戦が始まることになりますが、船会社も過去数年続いた不況期の経験を元にどのようにするかが注目ポイントだと思います。 そしてアメリカからのニュースの脱炭素船舶。今はニュースを見ると脱炭素、脱炭素と注目を集めているこのテーマですが、やはり反対勢力もあるんですよね。 インフラを整えるにも多額の資金がが必要になりますし世界No.1のアメリカとしては先陣を切って進めていけるでしょうが、一方で途上国の場合は財源の問題もありますし、ガラッと変えるのは抵抗があるでしょう。 とはいえ、この脱炭素の課題は地球規模の対策なので、今後の進展にも注目です。 今回の物流ニュースはいかがだったでしょうか。 物流関係者もそうでない人にもわかるように物流ニュースをまとめてみました。今回参考にしたニュースのソースは概要欄にリンクを張っておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。 現場からは以上でーす!ありがとうございました。 2021年5月物流ニュース - 参照情報 ★コンテナ不足長期化も。「9月まで」見方広がる。港湾混雑 解消見えず★ ★北米西岸港、2カ月連続100万TEU超え。輸入、5月以降も高水準★ ★コンテナ運賃、北米東岸FEU当たり7000ドル超。上昇歯止めかからず★ ★IMO、SOLAS条約の一部改正。海上安全委、自動運航船ルール策定へ★ ★ベッセルズ・バリュー・マーケット・リポート★ ★Shipments Delayed: Ocean Carrier Shipping Times Surge in Supply-Chain Crunch★ ★U.S. Push for Carbon-Neutral Ships Expected to Reveal Industry Divisions★ ・Twitter で DM を送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedIn でメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/ お問い合わせは「ツイッター」と「LinkedIn」のみで承っております。