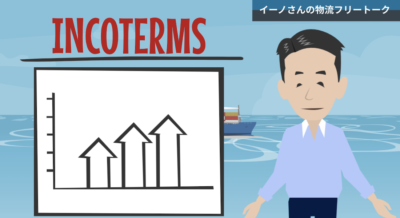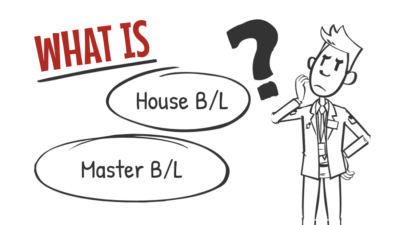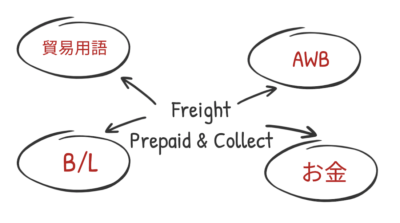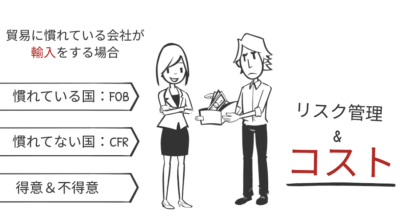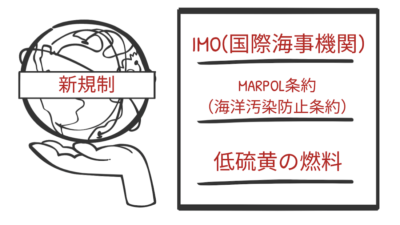
2020.11.28
LSSサーチャージについて
LSSサーチャージについて動画で解説 今回はLow Sulfur Surchargeについて解説をしていきたいと思います。 海上輸送に新しいサーチャージ 2020年1月から義務付けられた新しい規制により海上輸送に新たなサーチャージが加わりました。 船の燃料にLSC重油という低硫黄の燃料を使わなければいけませんよとIMO(国際海事機関)がマルポール条約、いわゆる海上汚染防止条約を改正したのです。 簡単に言えばこれまで使っていた環境に優しくない燃料をそのまま使うのはダメで、これからは低硫黄の環境に優しい燃料を使いましょうというルールです。 それでは詳しく解説をしていきましょう。 ご存知の通りPM2.5による大気汚染は国際的な問題になっていますよね。PM2.5は元をたどると排ガスに含まれる硫黄酸化物から生成されています。 PM2.5は具体的にどのような健康被害をもたらすかというと、肺癌や心疾患、そして小児喘息にもなってしまう可能性があるのです。 なので、あなたの健康を害するPM2.5を減らす為に、IMOはPM2.5を引き起こす排ガスの硫黄酸化物を減らそうというのが今回の規制です。 ローサーファーについて それではローサルファーとはどういう意味なのでしょうか? 硫黄を英語でいうとSulfurなので、Low Sulfurで低硫黄という意味になります。 従来、船舶で使われている燃料は主にC重油でした。 そのC重油に含まれる硫黄分濃度の上限は3.5%以下でなければいけなかったのですが 今回の条約改正で硫黄分濃度の上限が0.5%以下の「低硫黄重油」を使わなければいけないという決まりになったのです。 SOx規制 そして、この規制はSOx規制と呼ばれます。SOxとはSulfur Oxsideの略で硫黄化合物のことです。 このSOx規制で0.5%以下の低硫黄重油を使おうという条約改正は実は2008年に決まっていました。 しかし石油業界から、対応の準備期間が必要だとのことで、なんと12年の時間をかけて2020年1月の実施に至ったのです。 またこのマルポール条約では、排気ガスによる人の健康への影響は沿岸海域を運航する船舶からの方がより大きいことから、ECAと呼ばれる「指定海域」で規制を強化しています。 現在のECAは北米沿岸や北欧の北海・バルト海などがECAに指定されており、この海域の規制は更に厳しく、硫黄分濃度は0.1%以下でなくてはいけません。 では、必ず燃料をかえなければいけないのか?というとそうではありません。 スクラバーと呼ばれる排気ガス洗浄装置を船に設置することで従来のC重油の使用は可能です。 しかし、スクラバー設置には1機あたり数億円の設備投資が必要になり、さらに貨物積載のスペースも減ることになるとも言われています。 サーチャージが発生する理由 なぜサーチャージが発生するのでしょうか? 低硫黄燃料はこれまで使用可能だった従来のC重油よりも価格が高いので船会社も燃料費としてカバーしなければいけません。 またスクラバーを導入した船舶であれば、そのコストをカバーする為に船舶会社も費用補填をしなければいけません。 LSSはPM2.5を削減し、環境・人体に優しくするための環境コストとしてご理解頂ければと思います。 LSSの金額は? さてこの環境に優しくする為のLSSですが船会社によって金額が異なります。 このLSSが導入され始めると騒ぎになった2019年11月頃、私の会社も各船会社からの情報が不十分なまま、お客様に色々と質問をされました。導入時は各社とも他社の様子見な感じだったのかもしれません。 LSSにはタリフと売値があります。 タリフとは定価の事で、各船会社のHPで発表されていたりします。 船会社も各フォワーダーに対して同じLSSを提出しているところもあれば、安く価格を設定している船会社もあります。 一般的にLSSはタリフで3ヶ月間の固定ですが、弊社は特定の船社からはタリフより安い価格で提示をされ、毎月交渉をしています。 タリフであれば期間内は値上げはありませんが、お客様の為に交渉しているとLSSは上がることがありますのでご理解ください。 まとめ 国際物流には様々な機関が関係し定期的に規制が変わります。 環境や労務をより良くする為に規制は変わり続け、私たちはそれに合わせて事業を運営しなければいけません。 今回のLSSは地球環境の為に必要とされたもので、コストアップは辛いものではありますが、何卒ご理解を頂けましたら幸いです。 ・TwitterでDMを送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedInでメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/